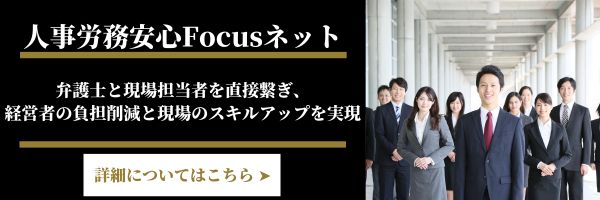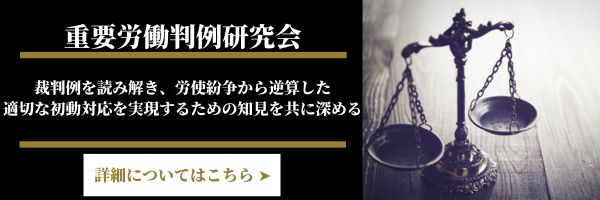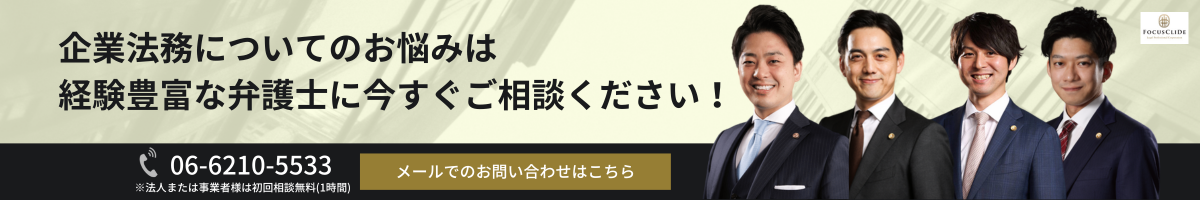コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
さて、本稿では、コロナ禍で相談が増えた「成果型賃金制度の導入」というテーマについて書かせていただきたいと思います。
コロナ禍で「成果型賃金制度の導入」を検討し始める企業様には、大きく分けて2種類のパターンがあるように思います。
1つ目
まず、コロナの影響を受けて売上が減少したことに伴い、経費(中でも割合が大きい人件費)を削減する1つの手段として、成果型賃金制度の導入を検討し始める企業様です(以下「経費削減パターン」といいます。)。
2つ目
次に、コロナの影響を受け、従業員の働き方を見直さざるを得なくなり、それに伴い、従業員1人あたりの生産性や成長度合いに着目し、限りある人件費を従業員に適正に分配することで、人材育成要素を賃金制度に組み込み仕組化する手段として、成果型賃金制度の導入を検討し始める企業様です(以下「人件費適正分配パターン」といいます。)
<経費削減パターン>
誰もが予測不可能であった新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、多くの企業様が迅速かつ適切な対応を余儀なくされる時代ですが、その対応の1つとして、売上げ減少に伴い経費を削減するという対応を取られた企業様は少なくないです。
この点に関して、興味深い調査データがあります。
2021年1月に東京商工リサーチが公開した「新型コロナウイルスによる業績上方修正」調査結果です。同調査では、2020年1月以降、適時開示情報において、業績を上方修正した上場企業のうち、新型コロナウイルス感染拡大の影響を理由にあげた企業様を集計しています。
2020年中に業績を上方修正した企業:551社
→上場企業全体(3837社)の14.3%に相当し、9月の前回調査から9.4ポイントのアップ
【業種別】
1位:製造業 214社(38.84%)
※特に食品・衛生用品・家電などの家庭内消費関連が大きく伸びた。
2位:小売業 88社(15.97%)
※スーパーやホームセンター等が巣ごもり需要で好調
3位:サービス業 84社(15.25%)
4位:情報・通信業 79社(14.34%)
※テレワーク・オンライン関連需要で好調
5位:卸売業 52社(9.44%)
6位:その他 34社(6.17%)
【理由別】
1位:経費削減 289社
2位:巣ごもり需要 163社
3位:内食需要増加 105社
4位:テレワーク需要の高まり 85社
以上の調査結果からもわかるとおり、業績を上方修正した上場企業の中でも、コロナ特需以外では、新型コロナウイルスの影響を踏まえて迅速かつ適切な経費削減を行った企業様がほとんどでした。
「新型コロナウイルスのお陰で」と表現すると語弊があるかもしれませんが、新型コロナウイルス感染拡大により、個人・法人を問わず、様々な局面で生活様式や行動の変革を余儀なくされたことで、これまで思考停止状態で垂れ流しになっていた無駄な経費、非効率な業務に対する経費等が浮き彫りになり(目をつぶれなくなり)、経費削減、そして最終利益の増加に成功したものと思われます。
このことからも、「経費削減の一手段として成果型賃金制度を導入する(コロナ禍で売上・利益が伸び悩み、成果を出すことができていない部署や個人の賃金を削減することによって、全体の人件費が削減するという目論見)」という経費削減パターンについては、「経費削減」という大きな方向性は正しいと思います。
しかし、前述の調査結果で経費削減により上方修正をした企業様でも、その実態は、直接的に賃金カットして経費を削減したというよりも、出張の自粛や、テレワークの普及により不要となった賃貸借契約を解約すること等によって、大幅に経費を削減した企業様が多いように見受けられます。
その理由の1つとして、そもそも成果型賃金制度を導入するということは、賃金カットされる従業員は当然のことながら、そうでなくても将来的に成果次第で賃金が減額されるリスクを伴うという意味で、全従業員にとって不利益な変更となります。そして、このような労働条件の不利益変更には、労働法上、様々な規制があり、一定のハードルが存在します。
そして、「コロナ禍で売上・利益が伸び悩み、成果を出すことができていない」としても、そのこと自体は経営責任の問題であり、従業員に責任転嫁すること自体に合理性を見出すことが困難であることが多いです。さらに、人件費総額の減少を伴う形で成果型賃金制度を導入する場合、制度を導入する必要性に加えて、人件費の削減をおこなう必要性があるかどうかまで考慮されることになり、有効性判断のハードルが大きく上がることになります。
そのため、経費削減パターンで成果型賃金制度を導入すること自体は、高いハードルがあるため、導入までに一定の時間・労力を要することになります。
当法人のHPに、下記関連記事を掲載しておりますので、ご参照ください。
・労働条件の不利益変更(総論)
https://fcd-lawoffice.com/labor/page-1434/
・紛争になり難い成果型賃金制度とは?
https://fcd-lawoffice.com/labor/page-1935/
<人件費適正分配パターン>
これに対して、人件費適正分配パターンは、経費削減を行うことが目的ではないため、人件費総額を維持されることが多く、成果型賃金制度導入の合理性は一定程度担保されやすい方向に働きます。
一昔前の日本企業に多く根付いていた年功序列型賃金制度では、社歴が長いというだけで、能力や成果に関係なく賃金が上昇し、いくら能力が高く成果を出している若い従業員がいたとしても、賃金としては反映されません。そのため、能力の高い従業員ほど離職しやすく、能力の低い重鎮ばかりが会社に残り、会社の業績の足を引っ張る傾向にあります。
そこで、従業員1人あたりの生産性や成長度合いに着目し、限りある人件費を従業員に適正に分配するという目的で成果型賃金制度を導入することは、従業員のモチベーションの向上、優秀な人材の確保に繋がり、企業の生産性・利益率の向上を期待することができます。
一方で、成果型賃金制度を導入するためには、前提として評価制度が必須となるため、そこで頭を悩ませるのが‘’評価項目の設定の仕方‘’です。
この点については顧問先からも良く相談を受けますが、私は、成果型賃金制度を「単に従業員の賃金を決定するためのもの」と位置付けるのではなく、「従業員の成長曲線を具体的かつ明確にする人材育成制度」と位置付けるべきと考えています。
企業成長の段階に合わせて、経営者が従業員に求める事項は変わってくると思いますが、その経営者が考える従業員の成長曲線に沿って、過半数の従業員が成長していけば、企業の成長スピードは格段に上がります。そして、これを実現する第一歩が、「経営者が考える従業員の成長曲線」を評価項目に反映することです。
そのためには、
- ①経営者の経営ビジョンを言語化し、
- ②当該経営ビジョンを実現するために必要な「理想の従業員の行動指針(自社では、従業員のどのような姿勢・考え方・行動を良しとするのかという指針)」を明確にした上で、
- ③当該行動指針を1つ1つ細分化・具体化して、評価項目に落とし込む
という手順を踏むことになります。これにより、経営者が考える従業員の成長曲線が評価項目に反映されることになります。
このような方法で作り上げられた成果型賃金制度の運用が定着すれば、従業員の成長が仕組化され、企業成長に大きく貢献することになります。
成果型賃金制度の導入を検討されている企業様は、その目的を再確認していただき、まずは<人件費適正配分パターン>で検討を開始してみていただければと思います。そして、その際は、是非一度、前述の①~③の手順で評価項目を設定することを試みていただければと思います。
また、既に成果型賃金制度を導入されている企業様においては、既存の評価項目が、経営者の考える経営ビジョンや行動指針と一貫し、かつ、その内容及び運営が透明化されているかをチェックしてみてください。
不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください!
執筆者:佐藤 康行
弁護士法人フォーカスクライド 代表弁護士。
2011年に弁護士登録以降、中小企業の予防法務・戦略法務に日々注力し、多数の顧問先企業を持つ。
中でも、人事労務(使用者側)、M&A支援を中心としており、労務問題については’’法廷闘争に発展する前に早期に解決する’’こと、M&Aにおいては’’M&A後の支援も見据えたトータルサポート’’をそれぞれ意識して、’’経営者目線での提案型’’のリーガルサービスを日々提供している。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?
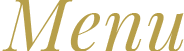

 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ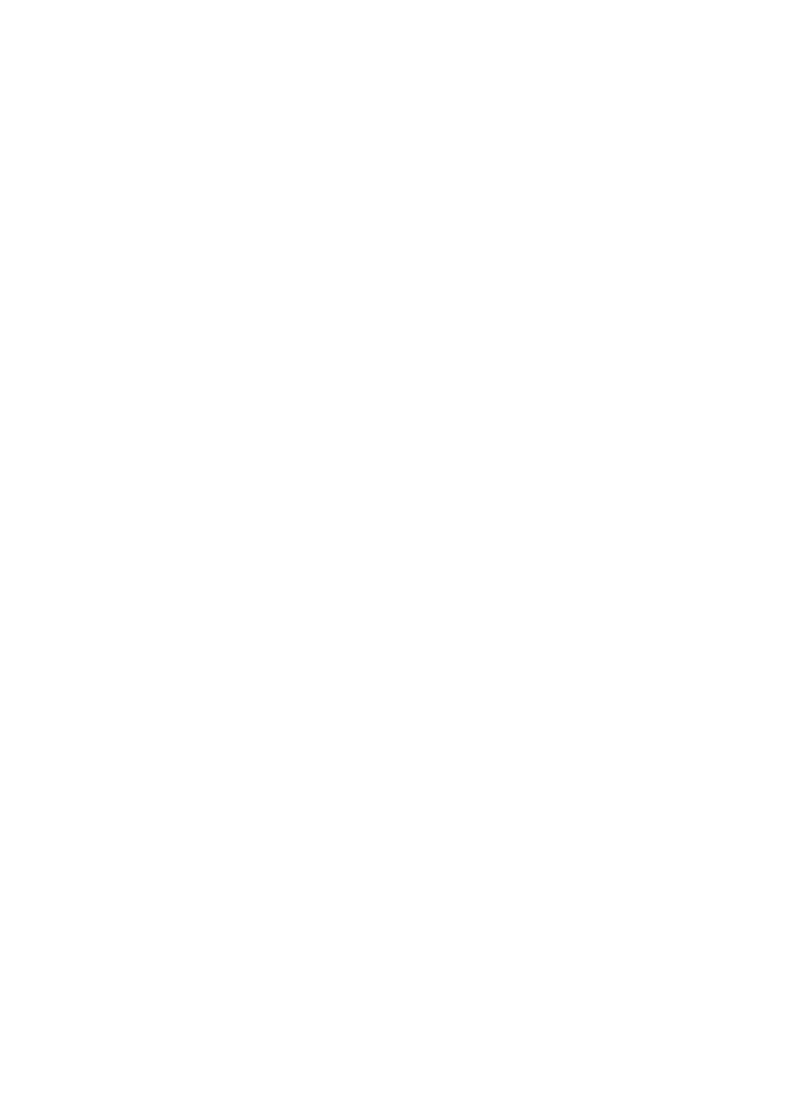 資料ダウンロード
資料ダウンロード