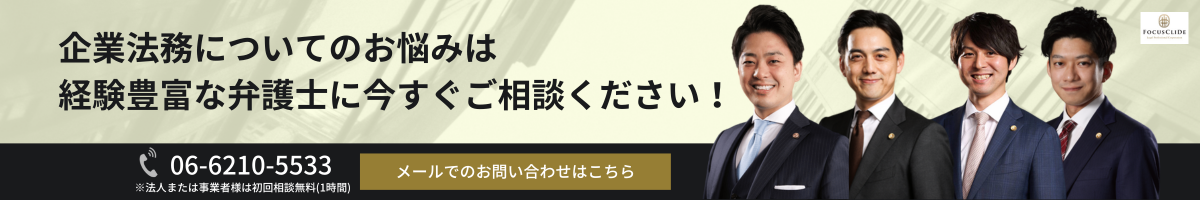正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
Contents
第1 はじめに
令和5年7月20日、最高裁において、正職員(無期労働契約)と定年後再雇用職員(有期労働契約。以下「嘱託職員」といいます。)との間における基本給や賞与の待遇差が(旧)労働契約法20条に違反するか否かについて判決が下されました(最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)。
本判決は、最高裁が正職員と嘱託職員との間における基本給の待遇差に関して初めて実質的な判断を示したものとして注目されており、企業の賃金制度に大きな影響を与えると考えられます。
第2 事案の概要
以下では、本件の第一審原告ら(嘱託職員)を「原告X1」、「原告X2」(総称する場合、「原告ら」といいます。)、第一審被告(株式会社)を「被告」といいます。
本件は、被告を定年退職した後に、被告と有期労働契約を締結していた原告らが、被告と無期労働契約を締結している正職員との比較における基本給、賞与等の待遇の相違は(旧)労働契約法20条に違反するものであったと主張して、被告に対し、不法行為等に基づき、上記待遇の相違に係る差額について損害賠償等を求めた事案です。
1 労働条件の相違、原告らの待遇について
正職員と嘱託職員の労働条件には、以下のような相違がありました。
| 労働条件 | 正職員 | 嘱託職員 |
| 就業規則 | 正職員に適用される就業規則及び給与規程 | 嘱託職員の賃金体系は勤務形態によりその都度決め、賃金額は本人の経歴、年齢その他の実態を考慮して決める 正職員定年退職時に比べ減額して支給される |
| 役付手当 | 正職員が主任以上の役職に就いている場合、当該役職の区分に応じて支給する | 支給なし 再雇用後は役職に就かない |
| 賞与 | 夏季及び年末の2回 各季の賞与は、各季で正職員一律に設定される掛け率を各正職員の基本給に乗じ、さらに当該正職員の勤務評定分(10段階)を加算する方法で算定される |
原則として支給しない 例外的に、正職員の賞与とは別に勤務成績を勘案して支給することがある 嘱託職員一時金として支給されていた |
原告X1は、正職員から嘱託職員になった際に賃金額が以下のとおり減額されました。
| 定年退職時 | 再雇用後 | 減額率 | |
| 基本給 | 月額18万1640円 | 1年目:月額8万1738円 2年目以降:月額7万4677円 |
41~45% |
| 賞与(1回当たり) | 平均約23万3000円 | 8万1427円~10万5877円 | 35~45% |
原告X2は、正職員から嘱託職員になった際に賃金額が以下のとおり減額されました。
| 定年退職時 | 再雇用後 | 減額率 | |
| 基本給 | 月額16万7250円 | 1年目:月額8万1700円 2年目以降:月額7万2700円 |
43~49% |
| 賞与(1回当たり) | 平均約25万5000円 | 7万3164円~10万7500円 | 29~42% |
2 職務内容等の異同について
原告らは、いずれも、正職員を定年退職し嘱託職員となって以降も、従前と同様に教習指導員として勤務をしていました。
再雇用に当たり主任の役職を退任したことを除いて、定年退職の前後で、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に相違はありませんでした。
また、当該職務の内容及び配置の変更の範囲にも相違はありませんでした。
つまり、(旧)労働契約法20条が具体的に明示する考慮要素について、原告らと正職員の間に相違はありませんでした。
参照:労働契約法20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
(下線部は執筆者が付記。)
なお、(旧)労働契約法20条は、現在、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条に引き継がれています。
参照:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇 のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
第3 名古屋地裁・高裁の判断
名古屋地裁・高裁は、基本給と賞与の相違について60%を下回る範囲で違法であると判断しました。名古屋高裁判決の判旨は以下のとおりです。
「原告らについては、定年退職の前後を通じて、主任の役職を退任したことを除き、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がなかったにもかかわらず、嘱託職員である原告らの基本給及び嘱託職員一時金の額は、定年退職時の正職員としての基本給及び賞与の額を大きく下回り、正職員の基本給に勤続年数に応じて増加する年功的性格があることから金額が抑制される傾向にある勤続短期正職員の基本給及び賞与の額をも下回っている。このような帰結は、労使自治が反映された結果でなく、労働者の生活保障の観点からも看過し難いことなどに鑑みると、正職員と嘱託職員である原告らとの間における労働条件の相違のうち、原告らの基本給が原告らの定年退職時の基本給の額の60%を下回る部分、及び原告らの嘱託職員一時金が原告らの定年退職時の基本給の60%に所定の掛け率を乗じて得た額を下回る部分は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。」(下線部は執筆者が付記。)
第4 最高裁の判断
1 判断の枠組み
最高裁は、(旧)労働契約法20条に違反するか否かの判断基準について、最高裁判決令和2年10月13日・メトロコマース事件を引用して、以下のとおり判示しました。
「労働契約法20条は、有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したもので あり、両者の間の労働条件の相違が基本給や賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである・・・。」(下線部は執筆者が付記。)
最高裁が示した上記判断枠組みは、従前最高裁が示してきたものと変わりはありませんが、基本給や賞与の待遇の差の場合も不合理と認められる余地があることを最高裁として初めて判示した上で、基本給や賞与の性質や支給目的等を考慮することが判示されています。
2 基本給について
⑴ 正職員の基本給に関する分析
最高裁は、まず、正職員の基本給の性質や支給目的を以下のとおり検討しています。
「上記事実関係によれば、管理職以外の正職員のうち所定の資格の取得から 1年以上勤務した者の基本給の額について、勤続年数による差異が大きいとまではいえないことからすると、正職員の基本給は、勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての性質のみを有するということはできず、職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質をも有するものとみる余地がある。他方で、正職員については、長期雇用を前提として、役職に就き、昇進することが想定されていたところ、一部の正職員には役付手当が別途支給されていたものの、その支給額は明らかでないこと、正職員の基本給には功績給も含まれていることなどに照らすと、その基本給は、職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質を有するものとみる余地もある。そして、前記事実関係からは、正職員に対して、上記のように様々な性質を有する可能性がある基本給を支給することとされた目的を確定することもできない。」(下線部は執筆者が付記。)
すなわち、最高裁は、一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するとしてものであったと指摘するにとどまった名古屋高裁の判断とは異なり、正職員の基本給には、職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質や職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質もあるから、基本給の支給目的が判然としないと指摘しました。
⑵ 正職員の基本給と嘱託職員の基本給の違い
次に、「前記事実関係によれば、嘱託職員は定年退職後再雇用された者であって、役職に就くことが想定されていないことに加え、その基本給が正職員の基本給とは異なる基準の下で支給され、原告らの嘱託職員としての基本給が勤続年数に応じて増額されることもなかったこと等からすると、嘱託職員の基本給は、正職員の基本給とは異なる性質や支給の目的を有するものとみるべきである」として、正職員と嘱託職員の各基本給は性質や支給目的が異なると認定しました。
⑶ 同一労働同一賃金ガイドラインの考え方
この点、同一賃金同一労働ガイドライン第3・1の脚注1には、「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に賃金の決定基準・ルールの相違がある場合の取扱い」として、「・・・当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない」とされています。すなわち、同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を踏まえますと、正職員と嘱託職員の各基本給の性質や支給目的を検討する必要がありましたが、名古屋高裁はそのような検討ができていませんでした。
そのため、最高裁は、「原審は、正職員の基本給につき、一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったとするにとどまり、他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない。」と判示しました。
⑷ 労使交渉に関する事情について
最高裁は、労使交渉に関する事情を(旧)労働契約法20条の「その他の事情」として考慮するに当たっては、「労働条件に係る合意の有無や内容といった労使交渉の結果のみならず、その具体的な経緯をも勘案すべき」と判示した上で、「上記労使交渉につき、その結果に着目するにとどまり、上記見直しの要求等に対する被告の回答やこれに対する上記労働組合等の反応の有無及び内容といった具体的な経緯を勘案していない」名古屋高裁の判断を批判しています。
⑸ 小括
最高裁は、名古屋高裁が正職員と嘱託職員の各基本給の性質や支給目的について十分に検討していないこと(上記⑴~⑶)、労使交渉の経緯を考慮していないこと(上記⑷)は違法であるとし、名古屋高裁判決を破棄し、もう一度審理を行うよう差し戻しました。
3 賞与について
賞与についても、正職員と嘱託職員の各賞与の性質や支給目的を検討していないこと、労使交渉の経緯を考慮していないことから、基本給とほぼ同じ理由で、名古屋高裁判決を破棄し、もう一度審理を行うよう差し戻しました。
第5 実務上の留意点
基本給の性質は企業によって様々であり、歴史的経緯もあるので、一律に決定することは困難ですが、本判決を踏まえますと、企業としては、自社の基本給制度について、その成り立ち・歴史的経緯を調べ、その性質や支給目的を明確にしておく必要があります。
その上で、非正規社員の賃金制度についても、その成り立ち・歴史的経緯を確認し、これを正規社員の賃金制度との違いとして説明できるようにする必要があります(ちなみに、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律14条2項には、非正規社員に対する正規社員との待遇差の内容や理由についての事業主の説明義務が定められています。)。非正規社員から正規社員との待遇差の内容や理由等について説明を求められた際に、その場で行き当たりばったりの説明をすることは、後々裁判になったときにも必ずベースになってくるため、非常に危険です。
また、本判決も判示するとおり、労働組合との交渉がある場合、その交渉経緯も重要ですので、この観点からも非正規社員と正規社員の賃金制度の相違について説明できるように準備しておくことが重要です。
第6 さいごに
以上のとおり、企業は、賃金制度の設計に際しては、賃金の性質や支給目的等を踏まえる必要があるとともに、非正規社員の賃金制度の設計に際しては、当該非正規社員の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲等も考慮する必要があるため、その考慮要素の多さや複雑さに悩まれることが多いと思います。
当事務所では、多数かつ多様な顧問先企業様の賃金制度に関するサポートをさせていただいてきた実績がありますので、就業規則の制定段階から将来の労使紛争の火種を作らないよう適切にサポートさせていただくことが可能です。
正規社員と非正規社員との間の待遇差に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合せください。
執筆者:山野 翔太郎
弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士。
2022年に弁護士登録。遺言・相続、交通事故、離婚・男女問題、労働、不動産賃貸者などの個人の一般民事事件・刑事事件から、企業間訴訟等の紛争対応、契約書作成、各種法令の遵守のための取り組みなどの企業法務まで、幅広い分野にわたってリーガルサービスを提供している。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ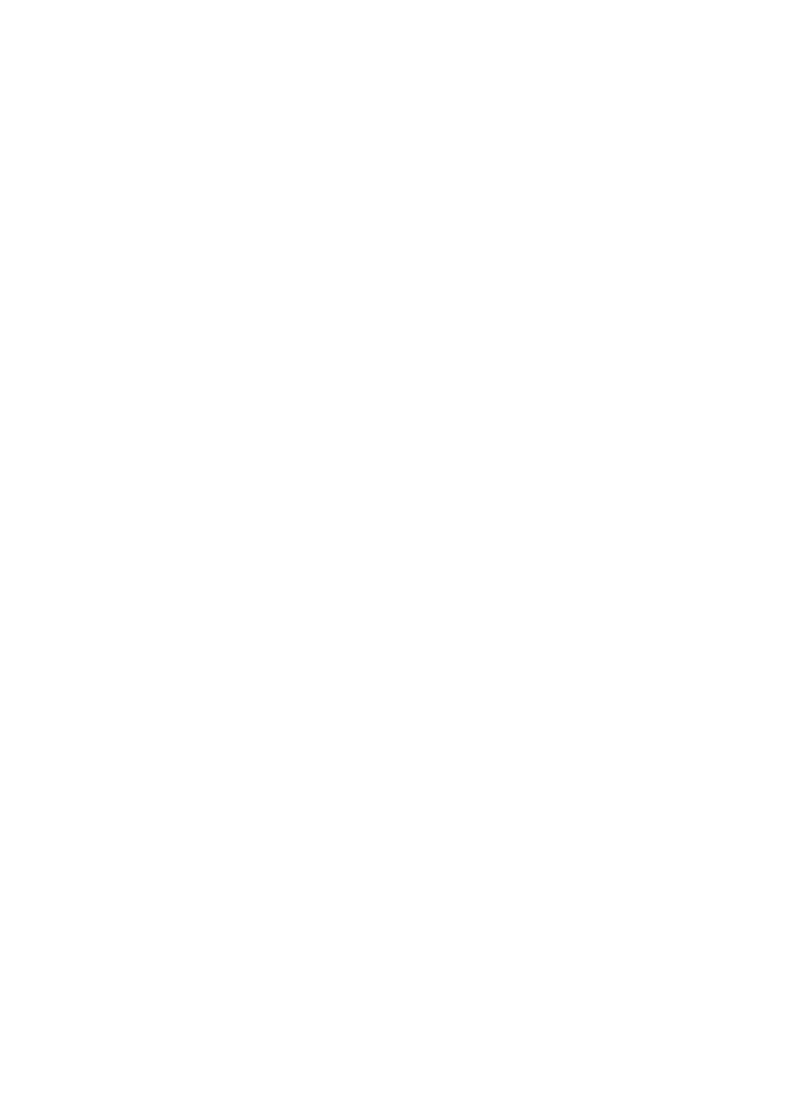 資料ダウンロード
資料ダウンロード