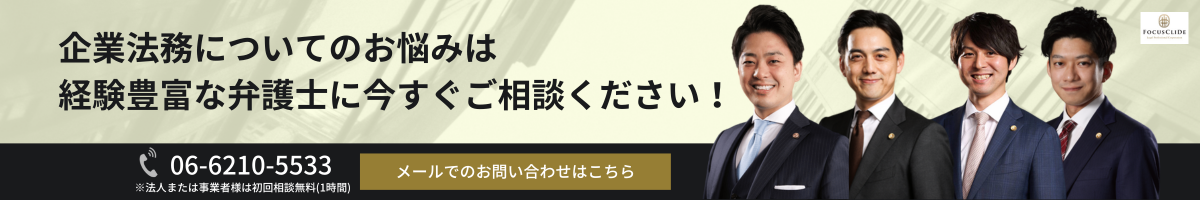退職勧奨を成功させるための3大要素
Contents
1.退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社から「合意による退職」を目指して退職に向けた説得活動を行うことをいいます。
2.退職勧奨の勧め
問題社員を退職させる方法として、一番に思いつく方法は「解雇」です。しかし、会社の紛争コストを最小化するという観点からは、「解雇」よりも「合意による退職」を実現することが望ましいといえます。その理由は、以下の3つです。
(1)解雇してしまうと会社の敗訴リスクが大きいため
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。つまり、日本において「解雇」が有効となるためには、①客観的合理性(雇用契約を終了させる(=労働者の生活の基盤を奪う)だけの客観的かつ合理的な理由があるか否か)と②社会的相当性(会社が「改善機会を付与したか」、労働者に「もはや改善する余地がないか」等)の2要件を充足する必要があるということです。
しかし、この①②の要件を充足するほどの具体的事実の主張立証に成功する事案は少なく、そのハードルは極めて高いのが現実です。そのため、解雇の有効性を争われた場合、会社が敗訴するというケースが非常に多いです。
(2)訴訟で敗訴した場合の会社のダメージが大きいため
解雇の有効性を争う訴訟で会社が敗訴した場合、会社は、解雇した従業員に対し、バックペイを支払った上で、当該従業員の雇用継続を強いられることになります。
バックペイとは、解雇された従業員が解雇日以降は働いていないにもかかわらず、解雇日以降の給料を全額遡って支払わなければならないという意味です。解雇が無効と認定された以上、従業員は雇用契約に基づいて労務提供しようとしたにもかかわらず、会社側がその労務提供を正当な理由なく拒否したのであり、従業員に落ち度はないということになってしまうためです。解雇無効確認訴訟は、訴訟が終結するまでに1年以上もの時間を要することがよくありますので、バックペイの金額は相当高額になることがあります。
このような高額なバックペイを支払った上で、さらに、会社が一度は解雇した従業員の雇用を継続しなければなりません。これは会社にとってはもちろんのこと、他の従業員に対しても多大な心理的ストレス等の悪影響を及ぼしかねません。
(3)裁判になれば費用と労力の負担が大きいため
さらに、解雇の有効性を争う訴訟を提起され、仮に会社側が勝訴したとしても、当該訴訟対応を弁護士に依頼すれば、相応の弁護士費用が発生してしまいます。
また、前述したとおり、訴訟が終結するまでに1年以上もの時間を要することがあり、その間、社長や関係従業員が何度も弁護士と打合せをしたり、資料を準備したり、尋問期日に出頭しなければならない等、生産性のない時間を多く費やさなければならなくなります。
このように紛争化した時点で、会社は有形・無形の多大な損失を被ることになります。
(4)小括
以上の理由より、会社の紛争コストを最小化するという観点からは、「解雇」よりも「合意による退職」を実現することが望ましいのです。
そして、前述のとおり、この「合意による退職」を目指して、会社から退職に向けた説得活動を行うことを退職勧奨といいます。
3.退職勧奨を成功させるための3大要素
退職勧奨を試みたものの、従業員がそれに応じず、苦労したという経験はないでしょうか。
退職勧奨はあくまで「説得活動」に過ぎませんので、当然、退職を強要することはできません。そのため、従業員が、会社の退職勧奨を受け、自ら退職の意思表示を行うことが必要です。
これを実現するために重要な要素は、次の3点にあると考えます。中でも①が最も重要な要素となります。
- ① 自己認識のゆがみを修正させる努力を惜しまないこと
- ② 予算を確保すること
- ③ 会社都合退職扱いとすることを説明すること
(1)自己認識のゆがみを修正させる努力を惜しまないこと
そもそも問題社員は、経営者や上司の気持ちを察することができないタイプが多く、会社が自分の扱いに困っているなど気づいていないか、あるいは気づいていたとしても気にもしていないことが多く見受けられます。問題社員自身は、「自分はちゃんとできている、正しい」と思っているのです。
問題社員が「自分は正しい」と思っている状態で、金銭的な補償をいくら提示しても納得しませんので、退職勧奨は失敗に終わってしまう場合が多いです。
そこで、退職勧奨を実施する準備として、問題社員との面談の場を設定した上で、問題社員に自分が職場の要求水準を満たしていないということをはっきり認識させる(自己認識のゆがみを修正する)ことから始めなければなりません。この努力を惜しむか否かによって、退職勧奨の成功率は大きく変わります。
自己認識のゆがみを修正させることを徹底した結果、金銭的補償の提示すらせずに、早期に退職勧奨を成功させることができた当事務所の解決事例については、以下の記事をご参照ください。
ローパフォーマーに対して、早期の自主退職を引き出した事例 | 弁護士法人フォーカスクライド (fcd-lawoffice.com)
(2)予算を確保すること
次に、極めて例外的な場面を除いて、問題社員から退職について早く確実に了解を得るためには、金銭的補償の提案が重要となります。
この予算の確保は、交渉の面においても重要な意味を有します。つまり、金銭的補償の提示をしなければ、「辞めるか、それとも辞めないか」だけの議論になってしまいますが、金銭的補償の提示をすると、その金額が「低いのか、高いのか」という議論に話を移すことができます。この議論に話を移すことができれば、既に「退職」を前提としていることになり、かつ、自分自身が一旦前提とした話を覆すことは心理的にしづらくなりますので、最も重要なポイントである「退職することに合意してもらう」という点をクリアしやすくなります。
ここで、どの程度の予算を確保すれば良いかという点ですが、個人的には、問題社員の「給与3か月分」が最終の妥協点の1つの目安になると考えています。
給与の3か月分も支払うことがもったいないと思われる方もいらっしゃると思いますが、そうでもありません。会社から解雇したとしても、労基法上、30日分の解雇予告手当を支払う義務があり、かつ、未消化有給休暇(最大40日)が残っている人は、全て消化した上で退職することが多いため、結局は給与3か月分と変わらないことになるためです。そうであれば、未消化有給休暇の買取りも含めて給与3か月分相当額の解決金を支払った上で合意により退職してもらい、後日解雇の有効性を争われる紛争リスクを完全に排除しておく方が得策であることは明白です。
(3)会社都合退職扱いとすることを説明すること
最後に、退職理由について、自己都合退職ではなく、会社都合退職扱いとすること(会社からの退職勧奨に応じて従業員が退職する場合、雇用保険の給付においては、通常は会社都合退職扱いとなります。)、その結果、雇用保険の給付において優遇され、退職する従業員にとって有利な取扱いになることを説明することが重要です。
他方で、会社都合退職扱いとすることにより、会社に何らかの金銭的負担が発生するわけではありません(ただし、雇用関係の助成金を利用している場合は、会社都合退職事案が発生することで悪影響を受ける場合がありますので、ご留意ください。)。
(4)小括
以上のとおり、まずは自己認識のゆがみを修正させ、自分が職場の水準を満たしていないことをはっきり認識させられた段階で、3か月分の給与を受け取ることができ、かつ、会社都合退職扱いとなることで雇用保険給付においても優遇されることを理解すれば、退職勧奨の成功率は大きく向上します。
4.退職勧奨を実施する際には弁護士に相談すべき理由
退職勧奨を実施する面談においては、問題社員も身構えていることが多いので、問題社員は面談でのやり取りを全て録音していると思っておいた方が安全です。よく退職勧奨の適法性を争われる裁判において、退職勧奨を実施する面談時のやり取りが録音データとして証拠提出されることがあります。
そして、当該面談時の会話1つ1つを取り上げられ、退職勧奨の適法性が議論されることになりますので、退職勧奨を実施する面談においては全ての発言に最大限の注意を払う必要があります。そして、裁判において退職勧奨の適法性を争われることを常に想定しておかなければなりません。
裁判における退職勧奨の適法性の争われ方を具体的にイメージすることができるのは、これらの紛争事例を数多く経験し、熟知している弁護士のみです。
社会保険労務士の先生方の中には、退職勧奨に関する豊富な知識や経験をお持ちの先生もいらっしゃいますが、紛争事案において実際に代理人となって交渉又は訴訟を行っていないという点が弁護士との決定的な違いです。
そのため、退職勧奨のサポートについては弁護士に依頼すべき業務と考えています。
5.当事務所へのご依頼
退職勧奨を実施する上で最も重要な「自己認識のゆがみを修正させること」と言っても、当然ながら、問題社員ごとの性格等を考慮して進めなければなりませんので、案件ごとに留意点は大きく異なってきます。
当事務所は、特に使用者側の代理人として様々な労使紛争を扱っており、従業員の退職勧奨又はこれに関連する紛争事案についても数多く取り扱ってきましたので、クライアント企業様のニーズ、事案の特殊性等を踏まえ、高い専門性をもって、また経営者目線で、的確な退職勧奨サポートを行うことができます。
従業員の退職勧奨に関してご不明な点やご不安な事項があれば、まずはお気軽にご一報ください。
執筆者:佐藤 康行
弁護士法人フォーカスクライド 代表弁護士。
2011年に弁護士登録以降、中小企業の予防法務・戦略法務に日々注力し、多数の顧問先企業を持つ。
中でも、人事労務(使用者側)、M&A支援を中心としており、労務問題については’’法廷闘争に発展する前に早期に解決する’’こと、M&Aにおいては’’M&A後の支援も見据えたトータルサポート’’をそれぞれ意識して、’’経営者目線での提案型’’のリーガルサービスを日々提供している。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ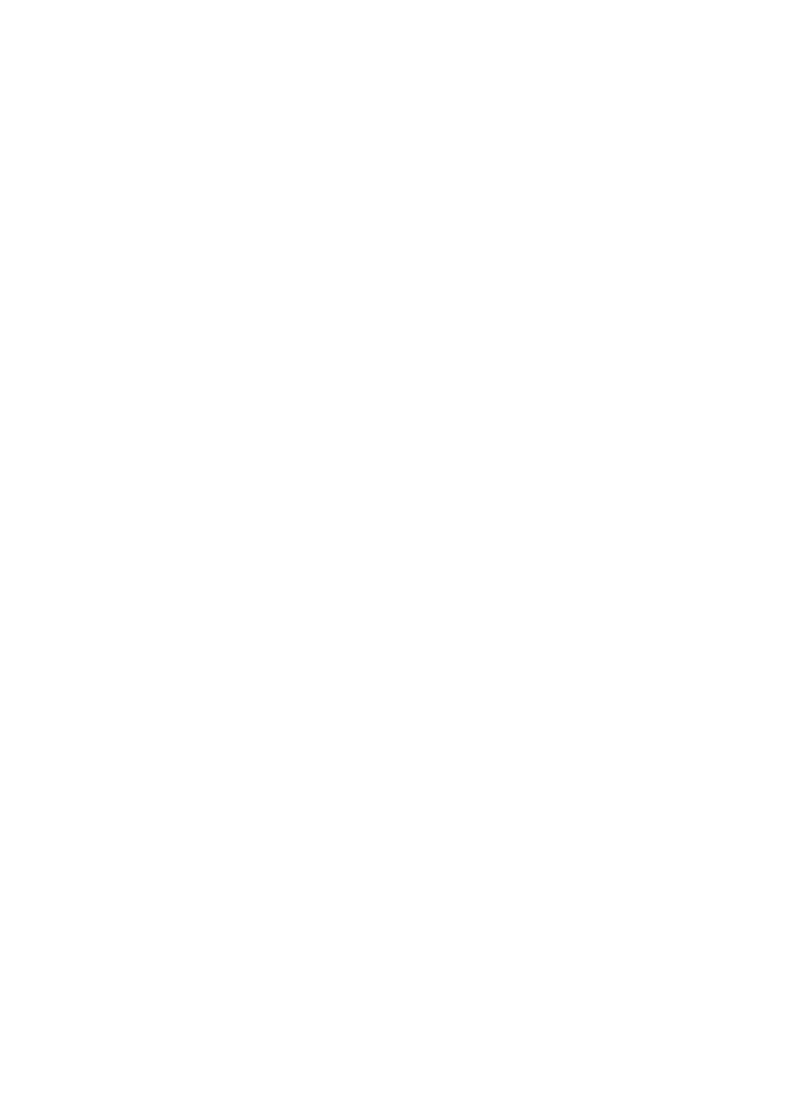 資料ダウンロード
資料ダウンロード