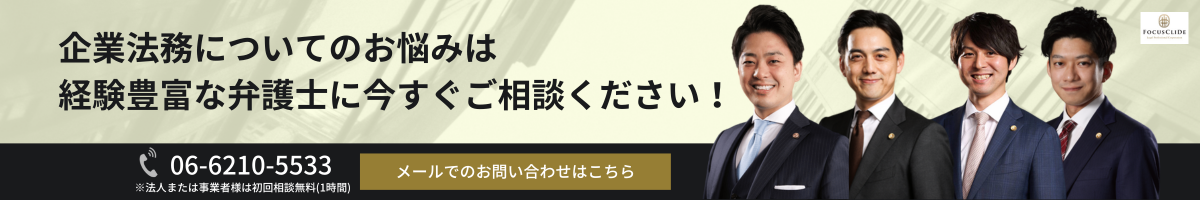【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
Contents
1 副業・兼業に関する動向とは?
副業・兼業を希望する従業員は年々増加傾向にあります。総務省の就業構造基本調査によると、平成24年の副業を希望する職業従事者は、約323万人(5.7%)であるのに対し、平成29年では約385万人(6.5%)と増加傾向にあります。また、副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまです。
一方、会社側でも、副業を認めていない会社の割合は減少傾向にあります。「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書」によると、副業を認めていない会社は約85%にものぼりましたが、令和2年に実施された調査によれば副業に消極的な会社は約7割にとどまり、残りの3割の会社においては、副業を明確に許容しているとの調査結果があります。会社側で副業に対して消極的な理由としては、生産性や売り上げが落ちると考えているから、利益相反や情報漏洩を懸念しているから、労務管理が困難だからなどが挙げられます。
このような中、厚生労働省では平成30年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定され、令和2年9月に同ガイドラインが改定されるなど、政策として会社に対してより積極的に副業・兼業を推進するよう求める流れができつつあります。
本稿では、副業・兼業についてどう対応すべきかお悩みの経営者・人事担当者の方向けに、副業・兼業のメリット・留意点、法規制等に関して総論的に解説させていただきます。
なお、制度導入にあたってのより具体的な留意点につきましては、別稿にて解説させていただきます。
2 副業・兼業のメリットと留意点とは?
⑴ 従業員側のメリット・留意点
副業・兼業の従業員のメリットとしては、①離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで従業員が主体的にキャリアを形成することができること、②本業の所得を活かして自分がやりたいことに挑戦でき自己実現を追求することができること、③所得が増加すること、④本業を続けつつよりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた 準備・試行ができることが挙げられます。
これに対し、副業・兼業による従業員の留意点としては、労働時間が長くなる可能性があるため、従業員自身による労働時間や健康の管理も一定程度必要であること、②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識する必要があること、③1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合があることが挙げられます。
⑵ 会社側のメリット・留意点
副業・兼業の会社のメリットとしては、①従業員が社内では得られない知識・スキルを獲得することができること、②従業員の自律性・自主性を促すことができること、③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上すること、④従業員が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで事業機会の拡大につながることが挙げられます。
これに対し、副業・兼業による会社の留意点としては、必要な労働時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要であることが挙げられます。
⑶ 従業員・会社側での留意点に関する対策
上記留意点のうち、労働時間の把握等につきましては、別稿でご説明させていただき、以下では、雇用契約に付随する各種義務の履行に関して具体的な対策をご説明いたします。
ア 安全配慮義務の遵守
会社は、雇用契約にともない、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負います(労働契約法第5条)。従業員が副業・兼業を行う場合には、副業・兼業を行う従業員を使用する全ての使用者がこの安全配慮義務を負うことになります。
副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、使用者が、従業員の全体としての業務量・時間が過重であることを把握しながら、何らの配慮をしないまま、従業員の健康に支障が生ずるに至った場合などが挙げられます。
この問題に対する対策としては、
- ① 就業規則、労働契約等において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと
- ② 副業・兼業の届出の際に、副業・兼業の内容について従業員の安全や健康に支障をもたらさないか確認するとともに、副業・兼業の状況の報告等について従業員と話し合っておくこと
- ③ 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について従業員からの報告等により把握し、従業員の健康状態に問題が認められた場合には、適切な措置を講ずること
等が考えられます。
イ 秘密保持義務の遵守
従業員は、一般的に雇用契約に付随する義務として使用者の業務上の秘密を守る義務(秘密保持義務)を負っています。
副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する従業員が業務上の秘密を他の使用者の下で漏洩する場合や、他の使用者の従業員が他の使用者の業務上の秘密を自らの下で漏洩する場合が考えられます。
この問題に対する対策としては、
- ① 入社時・新たに秘密情報に接触する機会がある度に秘密保持誓約書を締結したり、就業規則において業務上の秘密が漏洩等する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしてくこと
- ② 副業・兼業を行う従業員に対して、業務上の秘密となる情報の範囲や、業務上の秘密を漏洩しないことについて注意喚起すること
等が考えられます。
ウ 競業避止義務の遵守
従業員は、一般に、在職中、使用者と競合する業務を行わない義務を負っていると解されています(競業避止義務)。
副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する従業員が他の使用者の下でも労働することによって、自らに対して当該従業員が負う競業避止義務違反が生ずる場合や、他の使用者の従業員を自らの下でも労働させることによって、他の使用者に対して当該従業員が負う競業避止義務違反が生ずる場合が考えられます。
この問題に対する対策としては、
- ① 雇用契約時の誓約書や就業規則において、競業により、自社の正当な利益を害する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと
- ② 副業・兼業を行う従業員に対して、禁止される競業行為の範囲や、自社の正当な利益を害しないことについて注意喚起すること
- ③ 他社の従業員を自社でも使用する場合には、当該従業員が当該他社に対して負う競業避止義務に違反しないよう確認や注意喚起を行うこと
等が考えられます。
エ 誠実義務の遵守
従業員は、誠実義務に基づき、使用者の名誉・信用を毀損しないなど誠実に行動することが要請されます。
そのため、
- ① 雇用契約時の誓約書や就業規則において、自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができるようにしておくこと
- ② 副業・兼業の届出の際に、自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為をされるおそれがないか確認すること
等が考えられます。
3 従業員による副業・兼業は認めるべきか?
⑴ 副業・兼業に関する規制について
前述のとおり、副業・兼業を認めない会社が多数を占めている状況ではありますが、法的な観点からしますと、勤務時間外の時間を従業員がどう過ごすかは、基本的には従業員の自由です。
この点、副業を禁止する明文の法規制としては、公務員に関するものがあります。公務員については、国家公務員法や地方公務員法により、私会社からの隔離や、他の事業または事務の関与制限等が定められており、一部の例外を除いて、原則禁止とされています。他方で、民間会社では副業を制限する法的規制はなく、基本的には就業規則または雇用契約書等において、原則禁止とするもの、許可制とするもの、届出制とするものなど様々な形態があります。
⑵ 副業・兼業を禁止する規定の有効性について
このうち、副業・兼業を全面的に禁止する就業規則の規程は、従業員の自由の過度な制約となり、一部または全部が無効と判断されるリスクが高いと考えられます。たとえば、裁判例においても、「労働者は、勤務時間以外の時間については、事業場の外で自由に利用することができるのであり、使用者は、労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間を利用することを、原則として許さなければならない」と、原則として勤務時間外の副業を認める必要があるという判断がされています。
もっとも、副業・兼業を無制限に許してしまうと、副業・兼業先との競合・情報漏洩のリスク、本業の社会的信用を害するリスク、本業への支障や従業員の健康に問題が生じるなどのリスクが考えられます。
そこで、裁判例では、副業・兼業を例外的に制限できる場合として、
- ① 労務提供上の支障がある場合
- ② 業務上の秘密が漏洩する場合
- ③ 競業により自社の利益が害される場合
- ④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合と解されています。
これを踏まえて、厚生労働省の提示するモデル就業規則においても、原則として、従業員は副業・兼業を行うことができること、例外的に上記①から④のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができるとされています。
なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において従業員が副業・兼業を行う際に許可等の手続きを求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、違反に当たらないとして懲戒処分を認めず、また副業・兼業を理由とする解雇を無効であると判断されております。このため、従業員の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断する必要があります。
4 会社の基本的な対応
前記3のとおり、裁判例を踏まえれば、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが求められます。
そして、実際に副業・兼業を進めるに当たっては、従業員と会社の双方が納得できる内容で進めることができるように、従業員と会社との間で十分なコミュニケーションをとることが重要となります。このようなコミュニケーションをとりながら、会社は、従業員との間で、雇用契約や個別合意に基づく安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務等を履行できるように環境を整えて、副業・兼業を許容する方向が考えられます。
5 当事務所でできること
以上のとおり、世間においても、司法の世界においても副業・兼業を原則として許容する流れが進んでおり、従業員側でも副業・兼業を認めることが就職(再就職)の志望理由となること、あるいは副業・兼業を認めないことが、自己都合退職の原因となる可能性もありえます。しかし、これに適切に対応できている会社様はそれほど多くないというのが現実です。今後は、副業・兼業を許容する中で、いかに会社側で負うリスクを軽減できるかに重きをおき、日々の業務活動に注力するかが会社側に求められる基本的な姿勢となります。
当事務所では、副業・兼業の原則容認の第1歩としての就業規則の整備、労働時間の管理方法などの具体的な制度導入や、実際に運用するにあたっての業務フロー等に関して相談を受け、適宜アドバイスをさせていただいております。
実際に副業・兼業の申出を従業員から受けておられる会社様も,将来的に制度として導入を検討されている会社様も,お気軽にご相談ください。
執筆者:新留 治
弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士。
2016年に弁護士登録以降、個人案件から上場企業間のM&A、法人破産等の法人案件まで幅広い案件に携わっている。特に、人事労務分野において、突発的な残業代請求、不当解雇によるバックペイ請求、労基署調査などの対応はもちろん、問題従業員対応、社内規程整備といった日常的な相談対応により、いかに紛争を事前に予防することに注力し、クライアントファーストのリーガルサービスの提供を行っている。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ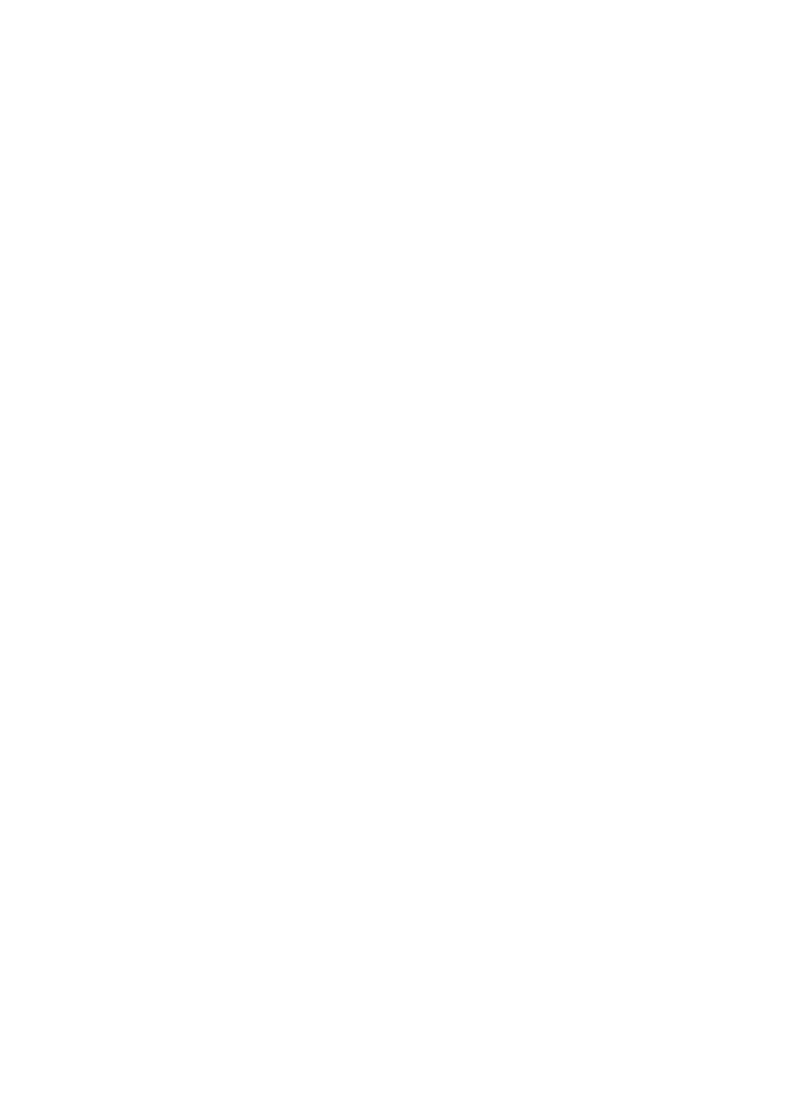 資料ダウンロード
資料ダウンロード