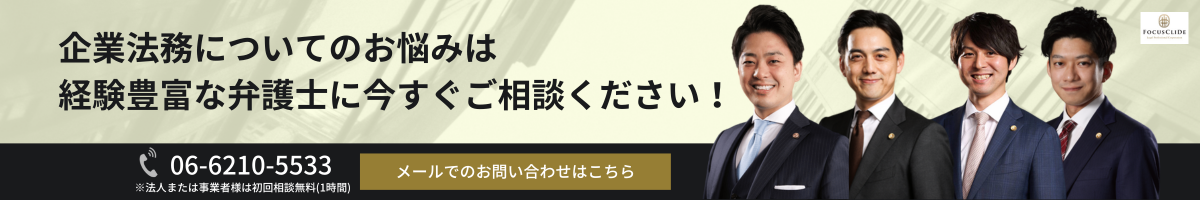性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
Contents
第1 はじめに
本記事は、「性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴」の続きになります。前回の記事(性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴ | 弁護士法人フォーカスクライド (fcd-lawoffice.com))では、性同一性障害を有する労働者が抱える悩みが顕在化する事案を把握するとともに、企業に求められている対応を検討するための素材として、服装と化粧に関する裁判例を取り上げました。
本記事では、通称とトイレ利用に関する裁判例を取り上げます。
第2 通称(大阪地判平成14年3月29日)
1 事案の概要
本件は、性同一性障害を有する労働者が当事者である裁判例ではございませんが、そのような労働者から自認している性(心理的な性)に適合する通称を使用したいとの申入れがあった場合の対応を検討するための素材として参考になります。
会社が従業員に対し婚姻性を名乗ること等を内容とする通告書を交付した点について、裁判所は以下のとおり判断しました。
2 裁判所の判断
「婚姻した姓の使用については、そもそも自己に対しいかなる呼称を用いるかは個人の自由に属する事項であることからすれば、合理的な理由もなくこれを制限することは許されない。会社は、夫の退職に伴い、婚姻姓を名乗っても支障がなくなったのだから、婚姻姓を名乗るように指示したと主張するが、会社の業務において、特に婚姻姓を名乗らなければならない必要性は証拠上認められないことからすれば、従業員に対し婚姻姓の使用を求める合理的な理由はないといわざるをえず、通告書という形式で、会社が、従業員に対し、婚姻姓の使用を命じたことは、従業員の人格権を違法に侵害するものであるから、これは会社による従業員に対する不法行為となる。」
3 求められる企業の対応
性同一性障害を有する労働者にとって、自認している性(心理的性)と一致しない名で自己を呼ばれたり識別されることは、大きな苦痛や違和感を伴うものです。
この裁判例を踏まえると、性同一性障害を有する労働者から自認している性(心理的な性)に適合する通称(裁判例では「姓」の使用が問題になっていますが、ここでは「名」の使用が問題になります。)を使用したいとの申入れがあった場合、企業が一律に通称の使用を禁止することは労働者の人格権を侵害するものとして違法となる可能性があります。企業が通称の使用を禁止する場合には、労働者に戸籍名の使用を求める合理的な理由が必要になります。
他方で、企業の立場からすると、人事・労務管理に当たり、同一性を把握する必要性があることから、戸籍名にて管理することは合理的であるとの主張が考えられます。しかし、職場において婚姻前の性を通称として使用することが広く認められるようになってきていることからすれば、性同一性障害を有する労働者が自認している性(心理的な性)に適合する通称を用いたとしても、通常、大きな支障や負担は生じないのではないかと思われます。
そのため、性同一性障害を有する労働者の意向に配慮し、通称を使用する場面と戸籍名を分けて、通称の使用を認めつつ、どうしても戸籍名を使用させなければならず通称の使用を制限し戸籍名の使用を命じる場合には、合理性があるかどうかを慎重に検討する必要性があるといえるでしょう。
第3 トイレ利用
1 事案の概要
本件は、身体的性別(生物学的な性別)が男性、自認している性別(心理的な性別)が女性のトランスジェンダー(Male to Female)であり、専門医から性同一性障害の診断を受けていた経済産業省の職員が、同省に対して、女性用トイレ使用の制限に関し、他の一般的な女性職員との公平な処遇を求めたという事案です。当該職員は、性別適合手術や性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律が規定する性別の取扱いの変更の審判を受けておらず、その戸籍上の性別も男性でした。
経産省は当該職員が勤務する場所から2階以上離れた階の女性用トイレの使用は認めたものの、庁舎管理権に基づき当該職員が勤務する階の女性用トイレ等の利用を禁止しました。当該職員は、当初は、勤務する階ではなく離れた階のトイレを利用することについて同意したものの、一定程度時間が経過し、当該職員が女性の身なりで勤務した時間も長期となり、周囲もそのような当該職員の勤務状況を受け入れていたなかで、当該職員が性自認についての説明会を開催しない限り自己の勤務する階の女性用トイレ等の利用禁止を継続していることが、国家賠償法上違法であるといえるか否かが問題となりました。
2 第一審(東京地判令和元年12月12日)
第一審は、このような経産省のトイレに関する処遇は、当該職員が「その真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることという重要な法的利益を制約するものである」ことに加えて、身体的性別又は戸籍上の性別が男性であることに伴って女性職員との間で生ずるおそれがあるトラブルを回避するために必要である旨の経産省の主張を前提にすれば、当該職員が「経産省の庁舎内において女性用トイレを制限なく使用するためには、その意思にかかわらず、性別適合手術を受けるほかないこととなり、そのことが当該職員の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約することになるという一面も有していることは否定することができない」としました。その上で、確かに「我が国や諸外国において、・・・必ずしも自認する性別のトイレ等の利用が画一的に認められているとまでは言い難い状況にある」ものの、「生物学的な区別を前提として男女別施設を利用している職員に対して求められる具体的な配慮の必要性や方法も、当該職員に係る個々の具体的な事情や社会的な状況の変化等に応じて、変わり得るものであるから」、「・・・直ちに上記のような性同一性障害である職員に対して自認する性別のトイレの使用を制限することで許容されるものということはできず、さらに、当該性同一性障害である職員に係る個々の具体的な事情や社会的な状況の変化等を踏まえて、その当否の判断を行うことが必要である」としました。
そして、本件では、当該職員が性同一性障害の専門医から適切な手順を経て性同一性障害と診断された者であること、経産省も当該職員が女性ホルモンの投与によって一定の時期までには女性に対して性的な危害を加える可能性が客観的にも低い状態に至っていたことを把握していたといえること、庁舎内の女性用トイレの構造からすると、利用者が他の利用者に見えるような態様で性器等を露出するような事態が生ずるとは考えにくいこと、当該職員は私的な時間や職場において社会生活を送るに当たって、行動様式や振る舞い、外見の点を含め、女性として認識される度合いが高いものであったこと、2000年代前半までに、当該職員と同様に身体的性別及び戸籍上の性別が男性、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員に対して、特に制限なく女性用トイレの使用を認めたと評することができる民間企業の例が証拠上も少なくとも6件存在し、経産省もこれらを把握できたこと、トランスジェンダーによる性自認に応じたトイレ等の男女別施設の利用をめぐる国民の意識や社会の受け止め方には、諸外国と同様に相応の変化が生じていることに照らせば、「他の女性職員とのトラブルが生ずる可能性は、せいぜい抽象的なものにとどまる」上、当該職員は「一貫して経産省が使用を認めた女性用トイレを使用しており、男性用トイレを使用していないこと」や、「女性の身なりで勤務するようになった当該職員が経産省の庁舎内において男性用トイレを使用することは、むしろ現実的なトラブルの発生の原因ともなる」等として、一定時点以降も当該職員が勤務する階の女性用トイレ等の利用を認めなかったことは違法であるとしました(なお、同判決は、多目的トイレの利用について、「性同一性障害の者は、そのことのみで直ちに同法[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律]第2条第1号に規定する高齢者、障害者等に該当するものとは解されず、少なくとも同法において多目的トイレの利用者として本来的に想定されているものと解されないし、当該職員にその利用を推奨することは、場合によりその特有の設備を利用しなければならない者による利用の妨げとなる可能性をも生じさせるものであることを否定することができない」としています。)。
3 控訴審(東京高判令和3年5月27日)
控訴審は、「自らの性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益である」として、第一審と同様に、性自認に基づく社会生活を送ることの法的利益の存在を肯定しました。
しかしながら、経産省は、当該職員から近い将来に性別適合手術を受けることを希望しており、そのためには職場での女性への性別移行も必要であるとの説明を受けて、当該職員の希望や主治医の意見も勘案した上で、対応指針案を策定して、同じ階の女性用トイレは利用させないが2階以上離れた階の女性用トイレは利用させるとしたのち、当該職員が性別適合手術を受けていない理由を確認しつつ、当該職員が戸籍上の性別変更をしないまま異動した場合の異動先における女性用トイレの使用等に関する経産省としての考え方を説明していたのであって、経産省において、当該職員との関係において、公務員が職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情があるとは認め難いとして、少なくとも国賠法の違法性は認められないと判断しました。その際には、性別の取扱いの変更の審判を受けていない性同一性障害を有する労働者に対するトイレ利用については今なお所属する団体や企業の裁量的判断に委ねられているとも判示しています。
4 求められる企業の対応
これらの裁判例を踏まえると、本記事の執筆時点(令和5年5月)では戸籍上の性別が変更された性同一性障害を有する労働者に対しては、当該変更後の戸籍上の性別に従ってトイレを利用させるべきですが、そうではない従業員、とりわけ、性別適合手術を行っていない場合には、そのトイレ利用等の処遇について、企業の合理的裁量に委ねられていると解するのが相当であると思料いたします。
そのような裁量を合理的に行使する上では、当該従業員の意向を尊重して女性用トイレを使わせることが、どの程度他の女性従業員の不安等を招くのか、逆に他の女性従業員の意向を尊重して女性用トイレを使わせないことが、どの程度当該従業員に対して不便や不利益を招くのか等を踏まえて判断すべきです。
いずれにせよ、企業として当該従業員及び他の女性従業員とのコミュニケーションを密にし、相互理解の向上を図ることが必要であり、また、相互理解の進展状況や社会的な変化等に応じて、なすべき対応も変わり得ることを踏まえて対応すべきでしょう。
なお、当該職員の上告を受けて、最高裁は令和5年4月16日、当事者双方の意見を聞く弁論を同年6月16日に開くことを決定しました。弁論は控訴審の判断を見直すために必要な手続きで、職場のトイレの使用制限について違法性は認められないとした控訴審・東京高裁の判断が見直される可能性があります。
第4 さいごに
以上のとおり、性同一性障害を有する労働者が抱える悩みは、人格権に関わるものであるため、企業においては、企業秩序を維持確保するために定める規則や指示・命令が当該労働者の権利を侵害することのないよう配慮する必要があります。
当事務所は、多数かつ様々な企業様の日々の労務管理について豊富な経験がございますので、LBGTをはじめとする労使関係に伴うお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆者:山野 翔太郎
弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士。
2022年に弁護士登録。遺言・相続、交通事故、離婚・男女問題、労働、不動産賃貸者などの個人の一般民事事件・刑事事件から、企業間訴訟等の紛争対応、契約書作成、各種法令の遵守のための取り組みなどの企業法務まで、幅広い分野にわたってリーガルサービスを提供している。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ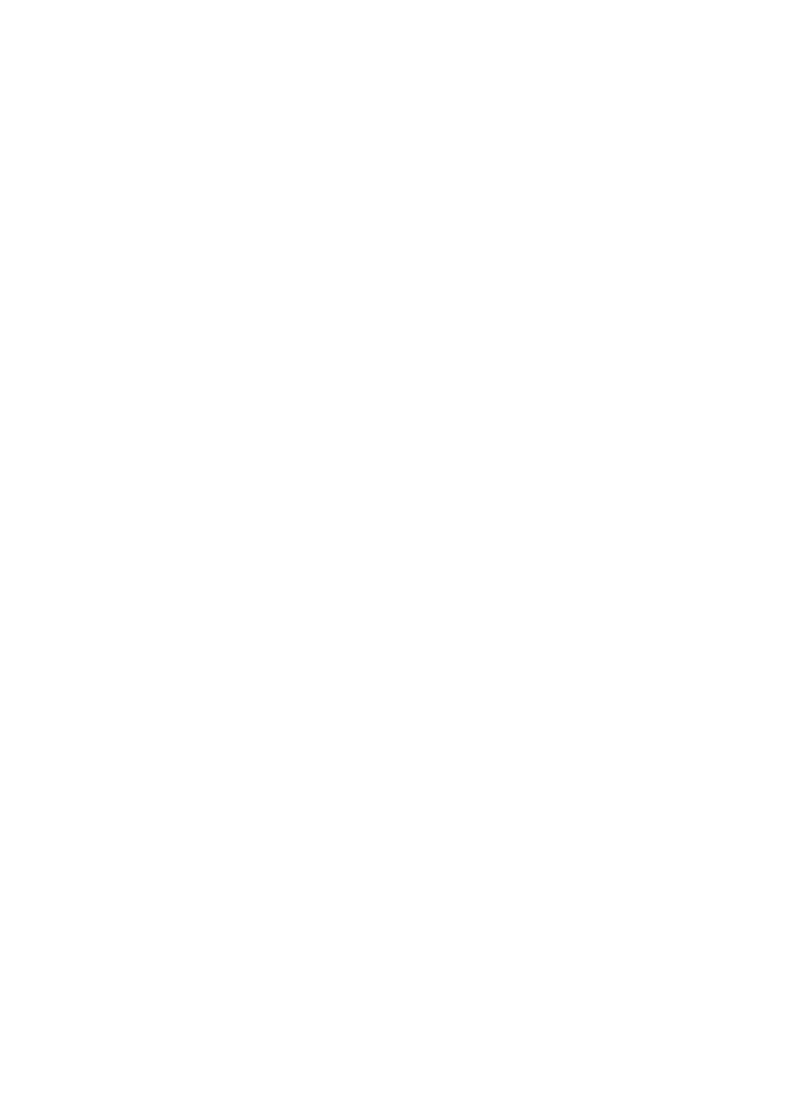 資料ダウンロード
資料ダウンロード