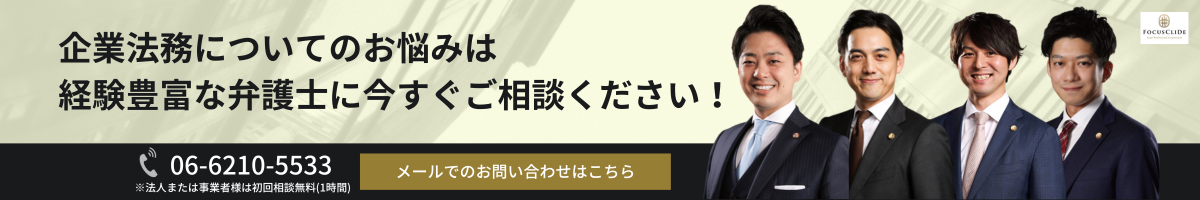紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
Labor IssuesContents
1. はじめに
残業代の支払いについては、特に紛争になりやすい論点の一つです。
これにはいくつかの要因がありますが、逆にいえばこれらの要因を可能な限り排除することにより、残業代の支払いに関する紛争を防止することが可能です。
そこで、本稿では、紛争になりやすいポイント及びその対策を説明することで、紛争になり難い残業代の支払い方法について説明いたします。
2.紛争になりやすい要因と対策
(1)要因1―管理監督者の設定
① 要因
労働基準法では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」について、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」を適用しないこととされています(労働基準法41条2号)。
この「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」を一般的に「管理監督者」と呼びます。
「管理監督者」に該当するか否かは、以下のような複数の要素によって決定されますので、形式的な役職等から自動的に該当性を判断することはできません。
A 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか
B 勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているか
C 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられているか
しかしながら、「管理監督者」という呼称から、会社でいわゆる管理職についている場合には、それをもって管理監督者に該当すると勘違いをされている会社も少なくありません。
管理監督者としての要件を満たしていないのにも関わらず、管理職についている、何らかの役職についているという理由で残業代を支払っていない場合、当該従業員について未払残業代が発生していることになります。
② 対策
「管理監督者」という名称に惑わされることなく、①で挙げたような要素をもとに、実質的に「管理監督者」の地位にあるといえるかを検討し、要件に該当する者のみを「管理監督者」として取り扱う運用に変更する必要があります。
この判断には、専門的な知識及び判断が必要になるので、会社の労務管理に強い専門家のアドバイスを踏まえて決定するのが紛争防止の観点からは有効です。
(2)要因2―固定残業手当制(みなし残業手当制)
①要因
近年、給与計算の簡略化や固定給を変更せずに従業員への支給総額増額等を理由として、固定残業制(みなし残業制)を導入する会社が多く見受けられます。
固定残業手当制が有効と認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があると解されています。また、就業規則・賃金規程を改定する必要もあります。
A基本給と固定残業手当部分を明確に区分すること
B固定残業手当には何時間分の残業時間に対応する手当を含むのか明示すること
C固定残業手当に対応する残業時間を超過した場合は別途割増賃金を支給すること
しかしながら、基本給と固定残業手当部分を区別せず、また固定残業手当に対応する残業時間の明示も行っていない場合や、固定残業手当に対応する残業時間数を超えても残業手当を支給しない(場合によっては、労働時間を正確に計算していない、あるいは計算方法を誤っていて支給できていない)ケースも少なくありません。
以上のように固定残業手当制が正しく運用できていない場合、未払残業代が発生してしまうことになります。
②対策
①で述べたとおり、固定残業手当制を適法に運用するためには、固定残業手当制の要件を満たす必要があります。
したがって、①記載のA~Cの要件を満たすように制度を設計し、また運用としても正確な労働時間管理に基づいて適切に残業代を支払う必要があります。
(3)要因3―年俸制
①要因
年俸制とは、給与を1年単位で決定する給与体系を指します。
年俸制は、それ自体が違法となる可能性が必ずしも高いというわけではありませんが、年俸制を採用すれば、残業代の支払いをしなくてもよいという誤った理解をしている会社が少なくありません。
しかしながら、年俸制の場合でも、原則として1日8時間、週40時間を超えて労働した場合には残業代を支払わなければなりません。
したがって、年俸制であることを理由にして残業代を支払っていない場合には、未払残業代が発生してしまうことになります。
②対策
年俸制を採用する場合でも、年俸制を採用していない場合と同様に、労働時間管理をしたうえで、残業が発生した場合には適切に残業代を支払う運用に変更する必要があります。
場合によっては、年俸制の採用の是非についても見直すのがよい場合もあるかもしれません。
(4)要因4-変形労働時間制
①要因
労働基準法では、変形労働時間制という制度を設けており、これを採用すると原則1日8時間、週40時間という労働時間の枠を超えて、柔軟に変形させることができます(労働基準法32条の2以下)。
変形期間は、1週間・1か月間・1年間という単位というパターンのほか、始業及び終業の時刻を自ら決定できるというフレックス制が存在します。
変形労働時間制を採用する場合でも、清算期間内で規定時間数を超える残業等があった場合には、残業代を支払う必要がありますが、計算方法が通常の労働時間制と比較すると複雑であるため、計算を誤って未払いが生じてしまうケースがあります。
②対策
まず、変形労働時間制を採用するためには、就業規則等に変形労働時間制を採用することを規定する必要があります。
また、そのうえで、未払残業代が生じないよう、変形労働時間制と清算期間に関する十分な理解のもとに適切に労働時間管理を行う必要があります。
(5)要因5―裁量労働制
①要因
裁量労働制とは、実労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間を働いたとみなす制度です(労働基準法38条の3、38条の4)。
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制が存在します。
裁量労働制が適用される場合、上記のとおり、実労働時間が法定の労働時間を超えていたとしても、あらかじめ定めておいた時間働いたものとみなされるため、残業代を支払う必要は生じません。
しかしながら、裁量労働制の適用が可能な労働者の範囲は厳しく、導入のための手続もやや複雑となっています。
そのため、本来は裁量労働制の要件を満たしていないにもかかわらず、安易に裁量労働制を採用して残業代を支払わない運用としてしまうと、未払残業代が発生してしまうことになります。
②対策
①で述べたとおり、裁量労働制の適用は非常に限定的にしか認められません。
そのため、本当に裁量労働制を適用できるのかどうかについて、十分に検討したうえで採用するか否かを決定し、裁量労働制を採用する場合には、適正な手続きに基づき導入を行う必要があります。
3.さいごに
労働基準法に基づく働き方には様々な制度が存在します。
しかしながら、それぞれの制度の適用範囲や導入のための必要手続き、導入後の適切な運用方法がそれぞれ異なっており、これを誤ってしまうと思わぬところで未払残業代が発生してしまうことになります。
各制度の内容については、解釈による部分もあり、専門家のアドバイスが不可欠です。
当事務所では、会社ごとに合わせた適切な制度設計からその具体的な導入手続きまでサポートを行っておりますので、未払残業代に関する紛争が発生し難い労働制度の設計をお考えの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
執筆者:櫻井 康憲
弁護士法人フォーカスクライド パートナー弁護士。
2016年に弁護士登録以降、上場直前期の企業のサポートに注力し、複数の企業の上場案件に関与した実績を有する。早期から弁護士との適切なコミュニケーションを行うことを通じて、必要最小限のコストで最大限の効果を発揮する予防法務の提供を実現するため、現在はスタートアップや上場準備会社を中心にコストを抑えてスタートできる顧問サービスの提供を行っている。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ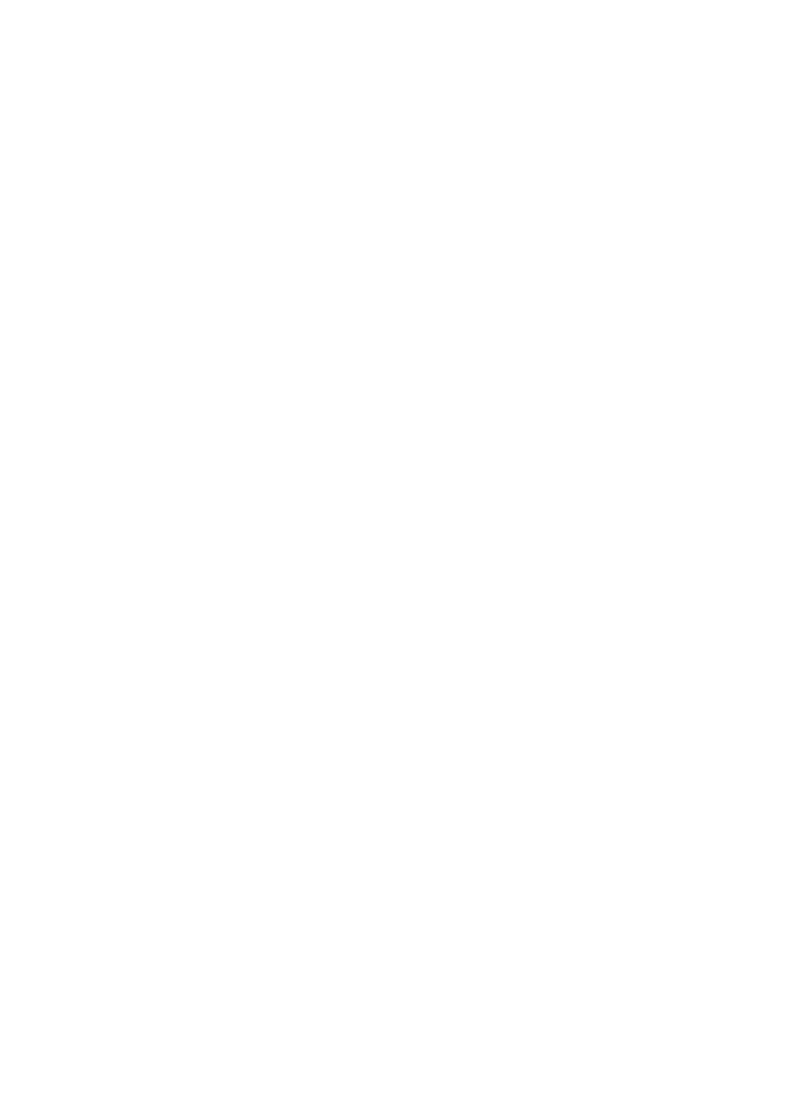 資料ダウンロード
資料ダウンロード