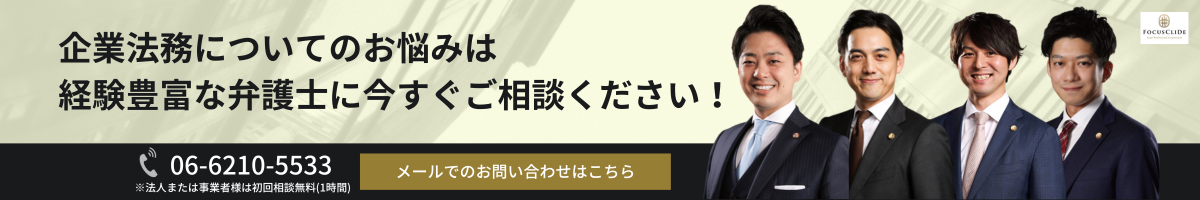退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
Contents
1 はじめに
従業員が会社を退職する際のトラブルは非常に多岐にわたります。
その一つとして,高額の留学費用,研修費用や資格取得費用を会社が負担したにもかかわらず,短期間で退職をしてしまうということがあります。
自社の業務効率をアップさせるため,各従業員のスキルアップなどの目的をもって,将来当該従業員が生み出す利益を見据えて,高額の留学費用,研修費用や資格取得費用を負担するというケースが多くあります。しかし,海外で一定の語学力や人脈を築いたり,専門的な資格やスキルを取得した従業員が,より高い報酬ややりがいを求めて転職したり,独立するという例も多く,早期に退職されることは,会社の費用負担が無に帰してしまうということにつながりかねません。
そこで,本稿では,万一早期に退職をした場合に,どのような方法であれば留学費用・研修費用の返還を求められるのかについてご紹介いたします。
2 早期退職の際に留学・研修費用の返還を求めることの問題点
労働基準法(以下「労基法」といいます。)第16条では,「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められております。当該労基法16条の趣旨は,違約金や損害賠償額の予定を定めることが歴史的にみて,労働者の不当な人身拘束につながった例があることから,そのような定めを排除することにあります。そのため,従業員が海外留学や高額の研修の終了後の一定の期間内に退職したときに,会社に対して当該費用の全額を返還しなければならないと約束することは,事実上労働関係の継続を強いることとなり,同条の趣旨に反するとも考えられるのです。
この点,実務においては,留学費用や研修費用の返還義務に関して,雇用契約とは別個の免除特約付き金銭消費貸借契約という形式が多く採用されております。つまり,使用者から留学対象や研修対象従業員に対して費用分の金銭が貸し付けられたに過ぎないのであって,従業員が一定期間,使用者のもとで勤務すれば恩恵的にこれを免除するというものです。これは,いわば従業員の自己啓発活動に対する福利厚生制度の一環という位置づけといえます。
このような形だけを見れば,従業員が退職した場合の留学費用・研修費用返還義務というものは,労基法第16条の「労働契約の不履行」とは全く関係がなく,単に金銭消費貸借契約上の問題に過ぎず,前述の労基法16条違反という問題は一切出てこないとも考えられます。
しかし,当然のことながら,実質を伴わない形式だけを整えることで労基法の適用を回避できるわけではなく,たとえ,上記の方法で,従業員と雇用契約とは別個に金銭消費貸借契約を締結したとしても,その実質が従業員の退職の自由を不当に制約するような足止め策であると判断されるのであれば,やはり労基法第16条の目的に反することになり,同条違反,金銭消費貸借契約を締結しているにもかかわらず返還義務が無効とされてしまうことになります。
3 労基法第16条に違反するかどうかの判断基準について
⑴ 「業務性」の程度について
それでは,どのような場合に留学費用・研修費用の返還義務が労基法第16条に違反すると判断されるでしょうか。この点を明確に述べた裁判例は存在しませんが,過去の留学費用の返還義務について判断した裁判例によると,基本的な視点は「当該留学・研修に関し,使用者と従業員のどちらがより多くの利益を享受する立場であるか」,ひいては留学・研修の「業務性」の程度がどれほど認められるかによるとされています。つまり,従業員が,当該留学・研修を業務の一環として行ったのか,それとも当該留学・研修はあくまで従業員個人の自己啓発活動としての側面が強いのかという点です。
さらに,この「業務性」の程度を判断するうえでの具体的な判断要素としては,以下の3つの要素が参考になります。
①当該留学・研修に関する従業員自身の自由選択・自由意思介在の程度
②留学・研修内容と従業員の業務との関連性の程度
③従業員個人にとっての当該留学・研修の有用性の程度
①の要素は,当該留学・研修が公募制あるいは従業員が自主的に申し込んだものなど,従業員の自発的意思に起因して行われたものか,それとも使用者側の一方的な人選により行われたものなのかという点が考慮されます。また,公募制など従業員の自発的意思に起因していると認められる場合でも,留学先,留学科目などの選択において従業員の判断が尊重されているか,現地での生活について干渉をしていないかなど留学内容についても考慮されます。
②の要素は,留学・研修内容と従業員の業務とが直接的に関連していると言える場合には「業務性」の程度を高めることになりますし,逆に留学・研修内容と従業員の業務が関連はしているものの,間接的なものにとどまる場合には,「業務性」の程度を低くすることになるという形で考慮されます。
③の要素は,当該留学・研修によって得られる成果が,当該会社特有のものではなく汎用性の高いものであって,退職後に別の勤務先でも有用性があるかどうかという点が考慮されます。有用性が高くないものであれば「業務性」の程度を高め,有用性が高いものであれば「業務性」の程度を低くすることになります。
上記の要素を総合的に判断して業務性がどの程度認められるかを検討することになります。
⑵ 返還額の相当性(返還義務免除の基準)について
労基法第16条に違反するか否かの判断基準として,返還額の相当性が問題となります。一般的には,返還義務が免除されるのは,留学・研修後一定の期間勤務を継続することですので,当該期間が長ければ長いほど,労基法16条の退職の自由の不当な制限に繋がり,無効と判断される可能性が高いです。また,返還を求める金額も,勤務を継続した期間にかかわらず常に「全額」とすることで,同様に退職の自由の不当な制限に繋がり,無効と判断される可能性がありえます。
この点,そもそも留学・研修費用の返還義務を定めるのは,会社の投下資本回収の必要性にあります。そうすると,投下された資本(=留学・研修費用)のうち,すでに回収されたといえる部分又はすでに回収不可能であるといえる部分については,留学・研修費用実費総額から差し引いた上で,従業員に対して請求するということが合理的といえます。そのため,会社は,当該留学・研修によって当該従業員が創出する利益を,留学・研修後どの程度の期間で回収することができるかを想定しつつ,仮に想定していた期間を待たずに退職をした場合でも,返還を求める金額を在職した期間に応じて減額するという方法をとることで,労基法第16条違反を回避できる可能性が高いことになります。
4 当事務所でできること
従業員の退職時に留学・研修費用の返還を求めることができるかどうかの判断基準については以上のとおりです。
留学・研修費用の返還を求めるには,単に免除特約付きの金銭消費貸借契約を締結しておけばよいという訳ではなく,当該留学・研修の「業務性」,返還額の相当性について検討をする必要があります。
当事務所では,顧問先企業様から返還の対象となる留学・研修の内容と当該従業員の業務内容を詳細にヒアリングしつつ,上記考慮要素と過去の事例に基づき返還義務を求めることが可能なものの選別及び返還額の決定方法,金銭消費貸借契約の条項作成などを適切にサポートさせていただいております。また,実際に,高額の留学・研修費用を支出したにもかかわらず,早期に退職した従業員に対して返還を求められないかというご相談も随時受け付けております。
従業員の留学・研修費用の返還に関するご相談をご希望の企業様は,是非一度お気軽にご相談ください。
執筆者:新留 治
弁護士法人フォーカスクライド アソシエイト弁護士。2016年に弁護士登録以降、個人案件から上場企業間のM&A、法人破産等の法人案件まで幅広い案件に携わっている。特に、人事労務分野において、突発的な残業代請求、不当解雇によるバックペイ請求、労基署調査などの対応はもちろん、問題従業員対応、社内規程整備といった日常的な相談対応により、いかに紛争を事前に予防することに注力し、クライアントファーストのリーガルサービスの提供を行っている。
- 求人票記載の労働条件と実際の労働条件が違ったら
~デイサービスA社事件~ - 同業他社への転職・独立による顧客奪取問題への対応方法について
- 内定後に実施したバックグラウンド調査を基に内定を取り消すことができるのか ~ドリームエクスチェンジ事件~
- 女性社員に対するマタニティハラスメントと言われないために ~妊娠を契機とする自由な意思に基づく退職合意~
- 2024年(令和6年)4月1日から労働条件を明示する際のルールが改正されます
- 正職員と嘱託職員の基本給と賞与の待遇差に関する最高裁判例 (最高裁判決令和5年7月20日・名古屋自動車学校事件)
- 残業時間にかかわらず賃金総額が固定されている給与体系が違法と判断された事例
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑵
- 【裁判例】休職・復職が問題になった事案に関して弁護士が解説
- 中小企業における割増賃金率の引き上げについて
- 電子マネー等による賃金のデジタル払い解禁について
- 性同一性障害を有する労働者をめぐる裁判例⑴
- 採用選考段階での留意事項について
- 【令和4年10月施行】出生時育児休業(産後パパ育休)に対する適切な対応を弁護士が解説
- コロナ禍で導入が進む成果主義的賃金制度
- 退職後の競業避止義務について弁護士が解説
- 【経営者必見】法令上作成義務のある労務書式12選
- 【経営者必見】労使紛争の回避又は労使紛争に勝つために重要な労務書式31選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説②【制度導入編】
- 【経営者必見】一定の要件を充足する場合に作成義務が発生する労務書式61選
- 【働き方改革】従業員の副業・兼業に対する適切な対応を弁護士が解説①【概要編】
- 退職勧奨を成功させるための具体的手順
- 退職勧奨を成功させるための3大要素
- 【改正パワハラ防止法】会社が講じるべき義務に対する適切な対応を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】適切な解雇理由書の作り方を弁護士が解説
- 残業時間の上限とは?押さえるべき残業時間上限規制のポイント
- 【絶対に揉めたくない】退職合意書の作り方を弁護士が解説
- 退職時に留学・研修費用の返還を求めることは適法?
- 経営者が知っておくべき最新の改正情報
- 中小企業が同一賃金同一労働に対してすべきこと
- 【絶対に揉めたくない】従業員の解雇について弁護士が解説
- 【絶対に揉めたくない】普通解雇について弁護士が解説
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 管理監督者について
- 固定残業代について
- 労働条件の不利益変更(総論)
- 紛争になり難い成果型賃金制度とは?
- 紛争になり難い残業代の支払い方法とは?
- 【経営者必見】解雇の前に認識すべき留意点
- 紛争になり難い雇止め方法とは?
- 紛争になり難い賃金・手当の減額とは?
- 年5日!年次有休休暇の取得義務化とその対策方法
- 【経営者必見!】紛争になりにくい定年後再雇用の注意点とは?


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ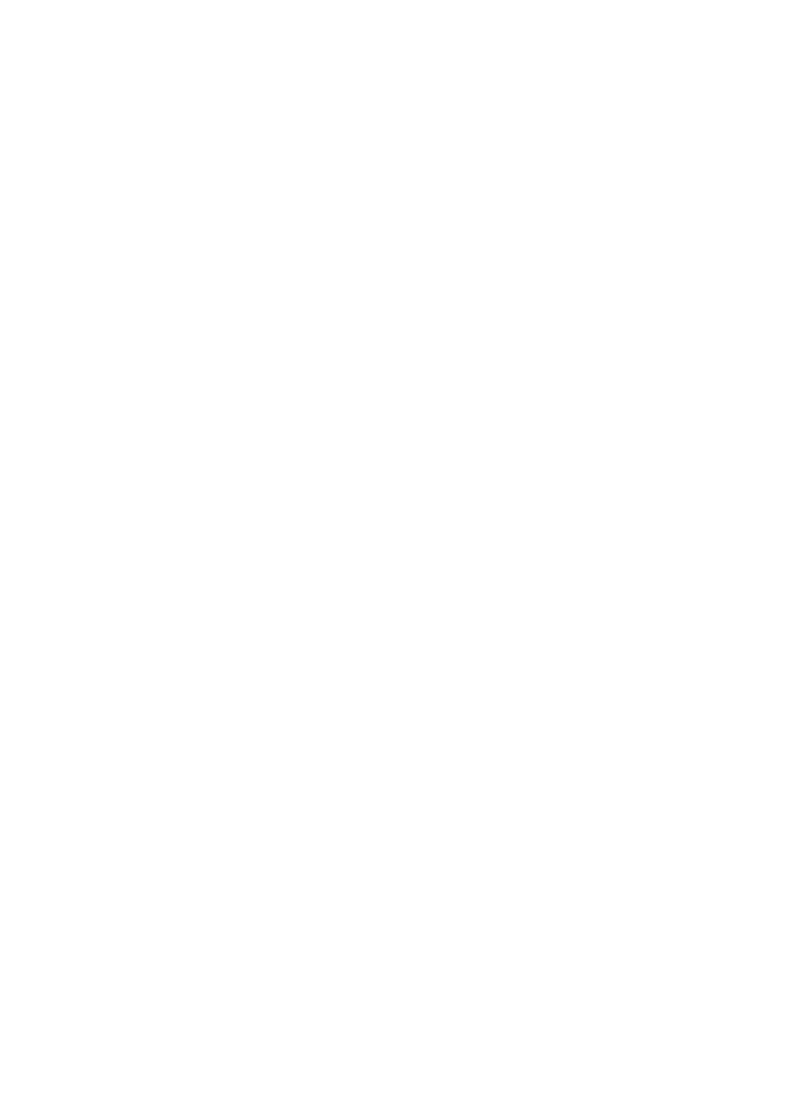 資料ダウンロード
資料ダウンロード