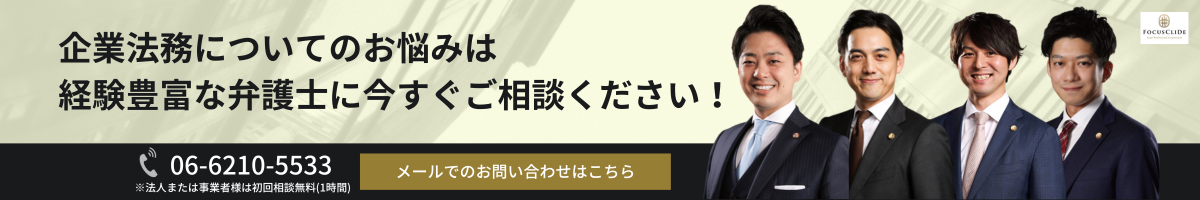事業承継と遺留分
1.遺留分制度の概要
事業承継対策を検討するにあたって必ず注意しなければならないのが、遺留分です。
今回は、この遺留分制度の概要と、事業承継対策における遺留分の位置づけ、遺留分対策の概要について説明します。
遺留分とは、相続財産のうち、相続人に最低限保障されている部分のことを言い、この取り分を侵害するような生前贈与や遺言が存在する場合、遺留分を侵害された相続人は、贈与や相続によって財産を取得した他の相続人に対して、「遺留分侵害額請求権」という、金銭の支払いを求める権利を有することとなります。
この権利が行使された場合、遺産の評価額や生前贈与の有無などにまつわる深刻な紛争に至るケースが多くあります。
被相続人の妻と子二人の事例における各相続人の法定相続分と遺留分の割合は下記のとおりです(遺留分の割合は、相続人の数や立場などによって異なります。)。
| 法定相続分 | 遺留分 | |
| 妻 | 1/2 | 1/4 |
| 子A | 1/4 | 1/8 |
| 子B | 1/4 | 1/8 |
相続人の生活保障などの目的で定められている遺留分制度ですが、2019年7月1日、抜本的な改正が行われました。具体的には、同年6月30日までに発生した相続については、遺留分を侵害する贈与・相続について、その効力を失わせる、という非常に強い効力が認められていました。
ご参考まで、改正前の民法における遺留分の具体例をご紹介します。
先代経営者にあたる被相続人が、後継者にあたる長男に事業用の土地建物(評価額1億1123万円)を、次男に預金1234万5678円を相続させる旨の遺言をして死亡した場合について検討します(被相続人の配偶者は既に死亡)。
次男の遺留分は4分の1、次男の遺留分を侵害する額は1854万8242円で、次男が「遺留分減殺請求権」(改正前民法で認められていた権利です。)を行使すると、次男は長男が取得した土地建物について、1億1123万分の1854万8242という天文学的な共有持分を取得することになるのです。そして、この共有関係の解消自体も、新たな紛争の火種になりかねない状況でした。
2.遺留分制度の改正
さて、2019年7月1日に施行された改正では、上記の「遺留分減殺請求権」という強すぎる権利について見直しが行われました。従来は、上記のとおり、次男の遺留分侵害の原因となった土地建物については、権利行使によって自動的に次男との共有となっていました(物権的効力が発生する、と表現されます。)が、改正法では、このような効果は発生しないことになりました。代わりに、上記事例における次男は、遺留分を侵害された分の金銭(1854万8242円)について、長男に対して、支払いを請求できることにされたのです(金銭債権化された、と表現されます。)。
また、遺留分に関する権利の性質の変更の他にも、重要な改正点があります。
改正前民法では、特別受益(相続財産の前渡しと言えるような、生前贈与のこと。)にあたるものであれば、共同相続人の一人に対する贈与は、時期的に無期限にさかのぼって遺留分算定基礎財産に算入するものとされていました。
このような規律に対しては、被相続人が、相続開始の何十年も前に行った相続人に対する贈与の存在により、当該受贈者や、その他の受遺者・受贈者が受ける減殺の範囲が大きく変動し、法的安定性を害するとの指摘がなされていたのです。
そこで、改正民法においては、相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前10年間にされたものに限って算入する、との規律に変更されまし。これにより、相続開始の10年前の日よりも前に生前贈与を行っておけば、遺留分の問題は生じないようにも思えます。この計算方法等を整理すると、以下のとおりです。
①相続開始前の1年間にされた贈与はその価額を遺留分算定基礎財産に算入する(1044条1項前段)
②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、相続の1年前の日よりも前にされたものであっても、その価額を遺留分算定基礎財産に算入する(同項後段)
③共同相続人の一人に対してされた贈与は、相続開始前の10年間にされたものであり、かつ、それが特別受益(903条)にあたるものである場合に限り、その価額を遺留分算定基礎財産に算入する(同条3項)
④当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与(共同相続人の一人に対して行われた特別受益にあたる贈与に限る)は、相続の10年前の日よりも前にされたものであっても、その価額を遺留分算定基礎財産に算入する(同条3項、1項後段)
このうち、④の規律には注意が必要です。ちなみに、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」について判例は、損害を加えることを知ってしたと言うためには、贈与当時に贈与財産の価額が残存財産の価額を超えることを知っていたというだけでは足りず、将来において相続開始までに自己(贈与者・被相続人)の財産が増加しないことの予見のもとで当該贈与がされたことを必要とする、としています(大判昭和11年6月17日民集15巻1246号)。
これに該当する場合、改正前と変わらず、数十年前の贈与についても遺留分算定基礎財産に算入される可能性があるのです。
3.事業承継における遺留分の位置づけ
以上の知識を前提として、事業承継の場面においてどのように遺留分対策を考えるべきか、検討してみましょう。
まず、事業承継における資産の承継に際しての2つの要請を確認します。特に中小企業においては、機動的な意思決定こそが大きな強みであり、多くの株主の意見に左右されない大胆かつ迅速な意思決定により、近年の流動的な経営環境の変化に対応することができると考えられます。また、株主管理コストは軽減したいというニーズもあります。
そこで、後継者の自由な意思決定権を確保できるよう、後継者に議決権を集約させることが望ましいと考えられます。目安としては、特別決議を可決させるために必要な3分の2、少なくとも普通決議を可決させることのできる過半数という議決権割合を確保させることになります。
他方で、複数のお子様がいるケースであれば、多くの経営者は、後継者に偏ってしまうことのないよう、財産を公平に分配してあげたいという希望をお持ちです。
そして、ここで遺留分への配慮も重要な要素となってくるのです。特に中小企業経営者の場合、個人財産に占める自社株式の割合が非常に大きく、後継者に株式を取得させようとすると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースも多くあります。
後継者に株式を集中的に承継しつつ、他の相続人の遺留分を侵害することなく公平に財産を分配する、この二つの要請をいかに満たしていくかが、円滑な事業承継を実現する上での最重要ポイントであると考えています。
なお、事業承継対策においては、どう税負担を軽くするか、という点から検討を始めてはなりません。繰り返しになりますが、先代経営者は財産をどのように分配したいと考えているのか、その中で、後継者への議決権の集中と、家族での財産の公平な分配をいかに実現するかを考えます。これを出発点として、その結果、税負担を資産し、納税資金を準備できるか、検証します。それが困難な場合に初めて、何らかの節税策、税負担軽減策を検討する、という順番です。
4.遺留分対策の手法
事業承継の場面では、改正前民法における、遺留分の侵害による株式の分散(物権的な効力がありますので、遺留分減殺の対象となった株式も共有状態に陥っていたのです。)は大きなリスクと考えられてきました。そのため、民法改正によって遺留分の強すぎる権利が見直され、金銭債権化されたことは、紛争を回避する上で大きな意義があります。
しかし、事業承継を実行する際に遺留分に配慮しなければ、後継者が後継者以外の相続人から遺留分侵害額請求権を行使され、多額の現金を準備しなければならないことになります。また、共有状態には陥らないとはいえ、株式をはじめとする相続財産等の評価で争いが生じた場合には、紛争が長期化する可能性はあります。残された家族を困らせてしまうことには変わりありませんので、これからも注意しなければなりません。
そこで、遺留分対策の代表的な手法をご紹介しておきましょう。
先代経営者の個人財産が自社株式に偏っていないのであれば、遺言で公平な分配を実現することは難しくありません。従って、先の例のように、個人財産の大部分が自社株式であるケースを想定します。このような場合に考えられる主な対策は、以下のとおりです。
①先代経営者から後継者へ株式を一部(全部)売買で承継(現金化)することで、分配の原資を準備
②後継者を受取人とする生命保険を活用して代償金を準備
③他の財産(生命保険を含む)を後継者以外の相続人に取得させ、遺留分放棄又は遺留分に関する民法の特例を活用
なお、②の対策は、財産の分配方法だけを見ると、後継者と後継者以外の相続人の間の不公平感が極めて高いものですので、他の方法で公平な分配を実現できないか、慎重な検討が必要でしょう。
5.さいごに
以上ご説明したとおり、円滑な事業承継とご相続の準備に際して、遺留分への配慮は非常に重要です。もちろん有効な対策方法はあるのですが、ケースバイケースで、専門的な対応が必要ですので、事業承継・相続対策について豊富な経験を有する弊所に、是非お気軽にご相談ください。
執筆者:伊藤 良太
弁護士法人フォーカスクライド パートナー弁護士。
中小企業の事業承継・相続対策及び資本政策を中心として、契約・労務・ガバナンス等の一般企業法務や、M&A、不動産案件も取り扱う。
事業承継については、経済産業省での執務経験も活かして、法務・税務横断的な提案を得意とし、事業と家族の双方に配慮した円滑・円満な承継に注力している。


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ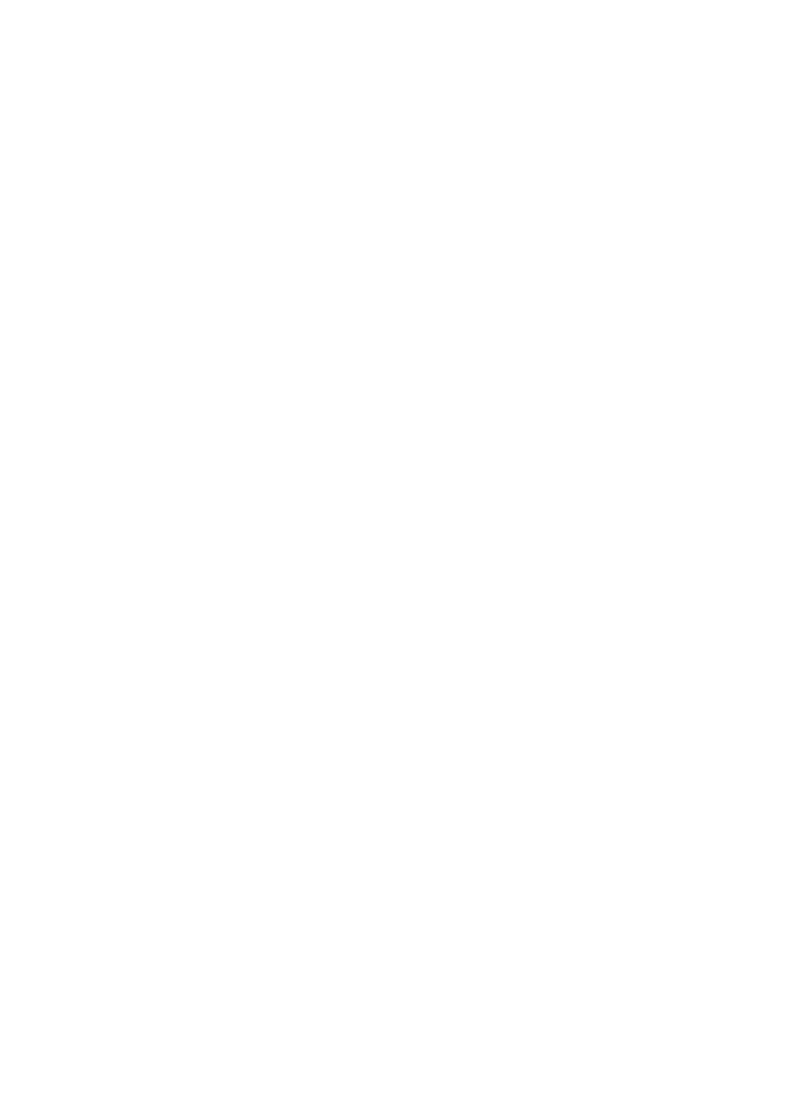 資料ダウンロード
資料ダウンロード