私が法律家を目指した理由を聞かれた際にいつも話すのは、私が小学生のころのある記憶です。
小学校の教室では、プリントを配布する際、教室前方の教卓の上にクラス全員分のプリントを乗せ、一人一枚ずつとっていく、という方法がとられることがあると思います。
私が覚えている光景の中では、ある時、そのようにプリントが配られた際、クラスのみんながわっと教卓に集まってしまって、なかなかスムーズに全員にプリントが行きわたらない、という状況が生じていました。私の記憶にあるのは、それを私が教室後方から眺めている、という状況です。私は、なんだか納得がいかない、適切でないような気持ちでそれを見ていたように思います。
その後中学、高校と進学し、さらに大学で法学を学ぶにつれて、“世の中の人たち自身にとって、ルールを守ったほうがメリットがより大きい場面がある”ということをより明確に考え、感じるようになりました。(ルールというのは、他人から押し付けられ、自分の利益を犠牲にして守ることを道徳的、倫理的に命じられる窮屈なもの、というイメージが強いと思いますが、そうではない場面もたくさんある、ということを学んでいきました。)
そして、私自身がルールの担い手となり、世の中の人々がもっと円滑に、納得して生活を送ることができるよう貢献したい、と思ったことが、私が法律家を志した理由です。
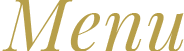

 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ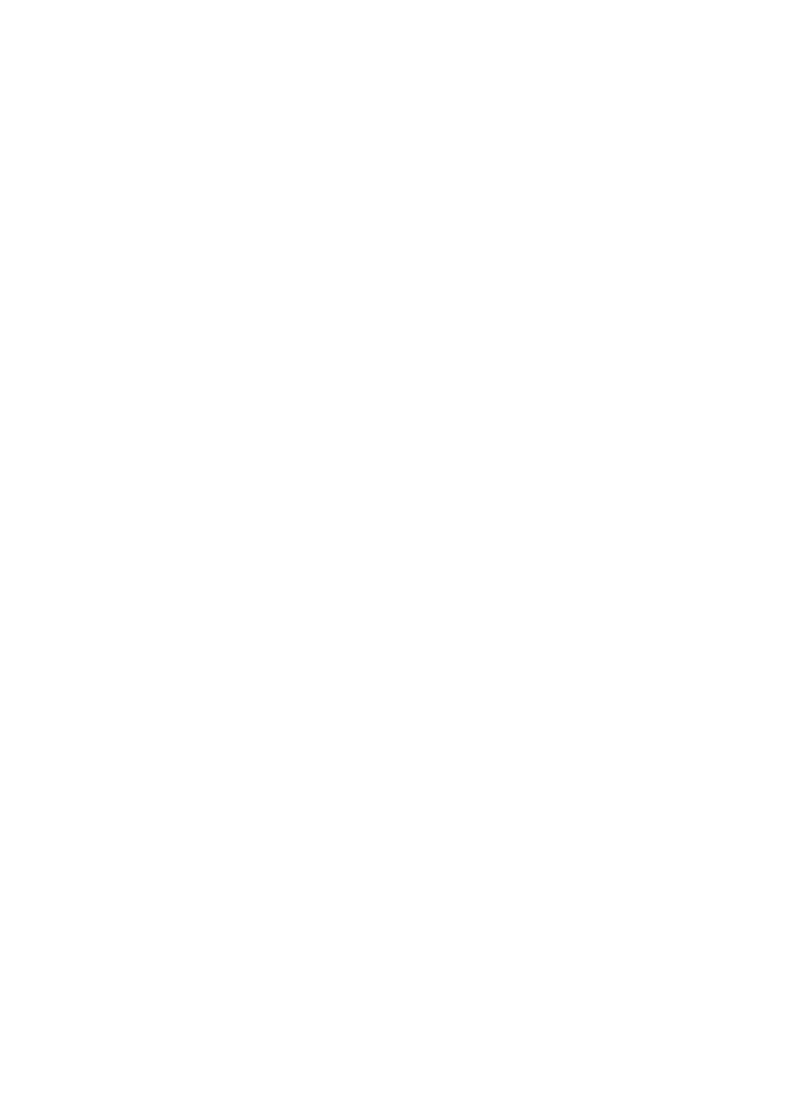 資料ダウンロード
資料ダウンロード