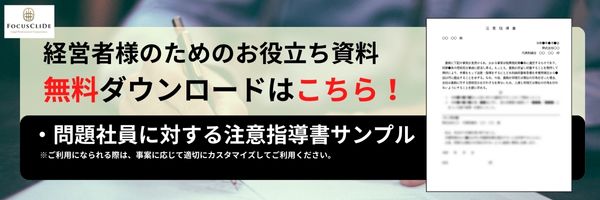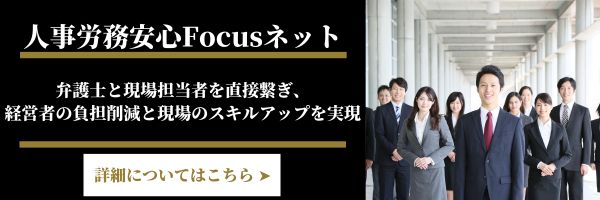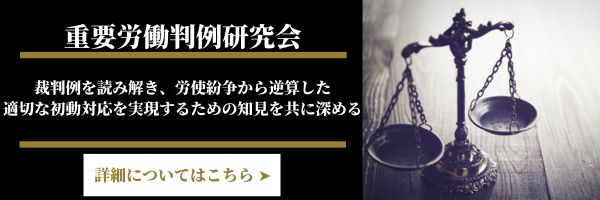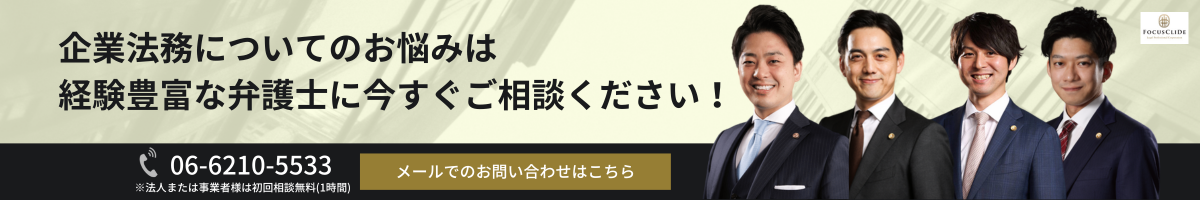【絶対揉めたくない】問題社員に対する注意書・指導書の作り方を弁護士が解説
Contents
1.はじめに
いわゆる問題社員と呼ばれる以下のような従業員への対応は、一歩間違えると会社にとって大きなトラブル・損害をもたらす可能性があります。
【問題社員の例】
・仕事をサボっている
・パフォーマンスが非常に低い
・無断欠勤、遅刻を繰り返す
・パワハラ、セクハラ等のハラスメントを行う
・残業代を稼ぐために、不必要な残業を行う
・体調、メンタルヘルスに不安がある
・他の社員との間で不和を生む
日本の法律上、上記のような問題社員であっても、その地位が非常に強く保護されていますので、いきなり解雇する、解雇までいかずともその他の懲戒処分や人事権の行使を行った場合には、解雇権や人事権の濫用として処分が無効となる可能性があります。
仮に解雇について裁判等で争われ、最終的に解雇が無効とされてしまった場合、解雇後の期間分の給与相当額を支払うことが求められる可能性が高いですし、このようなケースでは併せて未払残業代などに関する紛争にも発展することが少なくありません。
このような事態を招かないようにするためには、解雇その他の懲戒処分、人事権の行使が無効とならないための準備をしておくことが重要です。
そして、その準備として有効なのが、会社が問題社員に丁寧に指導を行い、それにも関わらずその問題社員が勤務態度を改善しなかったことについて、明確に記録し証拠化しておくことです。
(当然ながら、仮にこれらの注意・指導により勤務態度が改善するのであれば、それも一つの解決となります)
標準的な注意指導書のサンプルをダウンロードされたい方は こちら
※注意指導書サンプルはあくまで「サンプル」ですので、ご利用になられる際は、事案に応じて適切にカスタマイズしてご利用ください。
多くの裁判例においても、解雇や降格の前に、会社から度重なる注意・指導を受けていたにもかかわらず、問題社員の勤務態度に改善が見られなかったことを理由に、解雇等について有効と認めています。反対に、問題社員に対する指導が不足していた場合に、それを理由の一つとして、解雇等を無効と判断したケースも複数存在します。
以上の点を踏まえ、今回は、注意書・指導書の作成方法等についてご説明します。
2.なぜ書面で注意・指導を行う必要があるか
冒頭でご説明したとおり、問題社員に適切な注意・指導を行うことは、問題社員の勤務態度を改善するという意味でも、また、仮にその問題社員の勤務態度が改善しなかった場合に解雇、降格などの処分を行う上でも、極めて重要です。
注意・指導の方法としては、①口頭による方法と、②注意書・指導書といった書面で行う方法が考えられますが、注意書・指導書といった形で書面を作成して注意・指導をしている会社はあまり多くないのではないでしょうか?
口頭で注意・指導を行う方が、問題社員の問題行動が行われたそのタイミングで指導を行うことができますし、問題社員にとっても比較的受け入れやすいというメリットもあり、かつ会社側の事務的負担も少ないため、ほとんどの会社ではこの方法が取られているかと思います。
しかし、注意書・指導書といった書面での指導には、口頭の注意・指導にはない以下のようなメリットがあります。
・注意・指導を行った事実が記録として残ること
・直接的な注意・指導の内容に加え、その背景となる問題行動を含めた指摘も可能となること
・注意・指導の内容について認識の齟齬が比較的生じにくいこと
・問題社員が注意・指導を重大なものと捉え、勤務態度が改善する可能性が期待できること
もちろん、すべての注意や指導を書面で行うというのは、その事務的負担や問題社員を含む社員からの反発を招きやすいこと等を考慮すると、現実的ではありませんので、あくまで口頭での注意・指導に効果がなかったようなケースで書面による注意・指導を検討するという流れがよいと考えます。
3.注意書・指導書の作り方
口頭の注意・指導で効果がなかった場合に行う注意書・指導書の具体的な作り方・留意すべき点についてご説明します。
(1)問題行動を正確かつ具体的に記載すること
注意書・指導書においては、問題社員による問題行為につき、その時期や場所、行為の具体的な内容及びその背景について、正確に記載することが重要です。
仮に誤った内容が記載されていた場合には、却って問題社員からの反発を招く結果となり勤務態度改善に繋がりませんし、後々裁判等の紛争になった場合でも証拠としての価値がありません(むしろマイナスになる可能性すらあります)。
そのため、注意・指導を行うにあたっては、まず正確に問題行動の調査・事実確認をしておくのが重要です。
(2)具体的な改善方法を提示すること
問題行動の指摘があるだけでは、社員が具体的にどのように改善をすればよいか分からず、注意・指導を経ても勤務態度の改善に繋がらないことも考えられますし、また具体的な改善方法の指摘のない注意書・指導書では十分な注意・指導が行われたものとして評価されない可能性すらあります。
そこで、注意書・指導書を作成するにあたっては、問題行動それ自体の指摘に加え、具体的な改善方法を提案することが重要です。
これは、改善方法が必ずしも明確でない、能力不足の社員への注意・指導の場面では特に重要なポイントとなります。
(3)交付の時期
注意書・指導書の交付が問題行動から長期間経過したタイミングになってしまうと、事実上会社が問題行動を黙認していたとの評価に繋がりかねません。
そのため、注意書・指導書の交付は、問題行動からなるべく時期をあけずにタイムリーに行うよう心がける必要があります。
(4)受領欄を設けること
注意書・指導書は、問題社員に交付し内容を認識させてはじめて意味があるものです。
対面で交付した場合やメールその他のコミュニケーションツールで注意書・指導書を交付していても、問題社員が「気づかなかった」などと言われてしまうようでは、せっかく作成した注意書・指導書の効果が薄まってしまいます。
このような事態を防ぐためには、注意書・指導書の末尾などに、問題社員が注意書・指導書の内容を確認して改善を行うことを約束する旨の文言を付した受領欄を設けるのが効果的です。
4.おわりに
標準的な注意指導書のサンプルをダウンロードされたい方は こちら
今回は問題社員への対応において重要な注意書・指導書の作り方についてご説明しましたが、問題社員への対応は注意書・指導書を作成すれば足りるというものではなく、仮に問題行動が改善されなかった場合の対応や、そもそも問題社員を生み出さないための施策など、多くの検討すべき事項が存在します。
当事務所では、注意書・指導書の作成はもちろん、問題社員への対応全般や、問題社員を採用しない・生み出さないための環境づくりを含めた労働環境の整備についても多く取り扱っていますので、問題社員にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
執筆者:櫻井 康憲
弁護士法人フォーカスクライド パートナー弁護士。
2016年に弁護士登録以降、上場直前期の企業のサポートに注力し、複数の企業の上場案件に関与した実績を有する。早期から弁護士との適切なコミュニケーションを行うことを通じて、必要最小限のコストで最大限の効果を発揮する予防法務の提供を実現するため、現在はスタートアップや上場準備会社を中心にコストを抑えてスタートできる顧問サービスの提供を行っている。
下記のフォームを入力して、よろしければ送信ボタンを押してください。
- 美容室・美容院で窃盗や横領の疑いのある美容師・スタッフへの対応方法
- 【問題社員対応】私生活上の非行に対する懲戒処分の問題点について弁護士が解説
- 【問題社員対応】会社から貸与されたパソコンを私的に利用することの問題点について弁護士が解説
- 【問題社員対応】横領を疑われる社員に対する会社がとるべき対応について弁護士が解説
- 【揉めない人事労務】うつ病に罹患した従業員に対する労務管理について
- 【絶対放置できない】業務上横領が発覚した場合の適切な対処法を弁護士が解説
- 【絶対揉めたくない】問題社員に対する注意書・指導書の作り方を弁護士が解説
- セクハラ(セクシュアルハラスメント)を行う従業員にお困りの経営者様へ
- パワハラ(パワーハラスメント)を行う従業員にお困りの経営者様へ
- 問題社員(モンスター社員)の対応方法を労務に強い弁護士が解説
- 問題のある従業員対応に苦しんでいませんか①(パワハラ・セクハラ編)
- 問題のある従業員対応に苦しんでいませんか②(素行不良編)
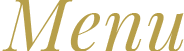

 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ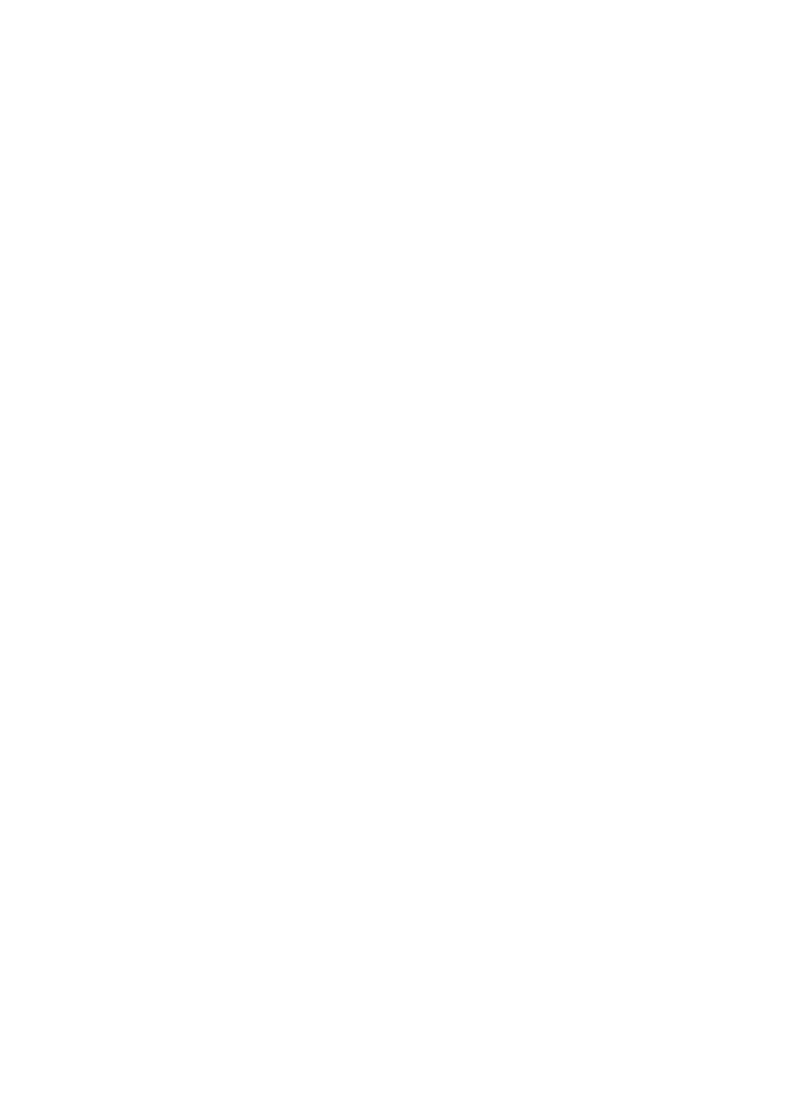 資料ダウンロード
資料ダウンロード