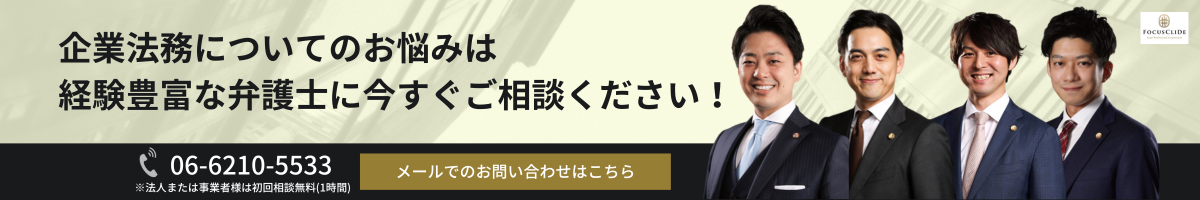事業譲渡した直後に売主側が同じ事業を立ち上げられたら?
M&Aの契約交渉においては、まずM&Aによって何を手に入れたいのかを明確にすることが大切です。このことを以下では、事例を交えて簡単に解説させていただきます。
ある日、弁護士宛てに、「学習塾事業の事業譲渡を受けたのですが、売主に同地域で新たに学習塾を立ち上げられ、講師も生徒も引き抜かれて、大損害を受けています。助けてください。」という趣旨の一通のメールが届きました。
事業譲渡スキームというM&Aにおいて、弁護士が作成した契約書が使用されていないということはないでしょうし、そうである以上、当然、事業譲渡後の競業避止義務の条項が設けられているはずですから、私は、上記相談メールを受信した時点では、「X社を救うことは容易だろう」と思っていました。
が…、実際に打合せをすると、状況はそう簡単なものではありませんでした。
Contents
【相談内容】
(※実際の相談内容を一部変更し、かつ、抽象化・簡略化しております。)
X社は、ある2つの地域(以下「地域α」と「地域β」といいます。)である学習塾を経営していたY社から、地域αでの当該事業の事業譲渡を受けました。そして、このうち、1校についてのみ塾生が相当多いマンモス校(以下「マンモス校」といいます。)で、残りは弱小校でした。そのため、X社としては、マンモス校だけの事業譲渡を受けたかったのですが、売主からはα地域の全てをセットでなければ事業譲渡しないと言われたため、弱小校とセットで事業譲渡を受けることにしたのです。つまり、本件事業譲渡において、このマンモス校がX社にとって重要校舎であったのです。
事業譲渡を受けた以上、X社としては、当然、事業譲渡後のY社は、地域αで学習塾を行うことをせずに、地域βのみで残った学習塾事業を行うと思っていました(常識的に考えてそうですよね。)。
しかし、事業譲渡の翌月に、地域αのマンモス校のすぐ近く(徒歩圏内)に新しい学習塾が開設されました(以下「新学習塾」といいます。)。なお、この新学習塾の運営会社は、Y社ではなく、Z社でした(調査したところ、Z社は、事業譲渡実行日の翌月に新設された会社でした。)。
それだけでなく、もともとマンモス校の人気講師であったAさんが、Y社からX社への雇用契約の承継を拒否したうえで、Z社へ再就職し、この新学習塾の人気講師となったのです。人気講師であったAさんの影響力は大きく、Aさんがいなくなったマンモス校からは生徒がどんどん流出し、事業譲渡後わずか3カ月程度で、売上は4分の1程度まで激減してしまいました。
【X社の油断】
事案の概要を把握した私は、すぐに事業譲渡契約書を確認しました。
しかし、事業譲渡契約書は存在したものの、同契約では売主側に競業避止義務が一切課されていなかったのです。また、人気講師Aさんの流出を防ぐためのリスクヘッジも何もされていない非常に簡単な事業譲渡契約書でした。
なぜ、このような杜撰な契約書で本件事業譲渡を進めたのか、その理由を聞くと、「今回の学習塾事業は、フランチャイズの学習塾(加盟店側=フランチャイジー)でして、フランチャイズの本部(フランチャイザー)から提供された契約書であったため、大丈夫だろう」と考えてしまい、特にリーガルチェックを入れずに進めてしまったとのことでした。
また、X社の社長は「まさかこんな詐欺みたいなことをされるとは思いもしませんでした。」ともつぶやいていました。
※事業譲渡における「競業避止義務」とは…
譲渡会社が、事業譲渡した日から一定期間、一定の地域において、譲渡した当該事業と同一の事業を行ってはならないという義務です。
当該義務が課せられる期間、地域、事業内容等の範囲は、契約において明確に定めることになります。
※会社法第21条に基づく「競業避止義務」とは…
以上のような契約条項が定められていない場合であっても、会社法第21条には、以下の範囲の競業避止義務が定められています。
記
- 1 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
- 2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
- 3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
【調査の必要性】
以上のとおり、契約による競業避止義務違反を主張することが困難な事案であることが判明しましたので、会社法第21条に基づく競業避止義務違反を理由に主張を組み立てる必要がありました。
しかし、新学習塾を運営しているのは、事業譲渡の売主である「Y社」ではなく、別会社である「Z社」でした。そのため、会社法第21条に直接違反するという状況でもありませんでした。
そのため、Y社とZ社を同視できるような特段の事情や、Y社が事業譲渡契約当初から、Z社の設立を画策していた等の特段の事情の有無を調査する必要がありました。
X社のお話を聞く限り、このZ社はほぼ間違いなく実態のない会社で、実質はY社による経営であることを疑わせる事情もありましたが、法的紛争となれば、推測ではなく、客観的証拠が必要となります。
そこで、調査会社を使って、Y社とZ社の資本関係等、上記特段の事情の有無を調べることとなりました(これにより、X社には、当然、当該調査のために一定の時間、労力、費用が発生してしまいます。)。
【どうすれば、このような事態を未然に防ぐことができたか】
事業譲渡契約を締結する前の早い段階で弁護士に相談して、交渉段階又は事業譲渡契約締結段階におけるリスクヘッジをしていれば(広く競業避止義務を課したり、人気講師Aさんが雇用契約承継を拒否した場合のリスクヘッジ条項を設ける等)、このような事態を未然に防ぐことができたということは容易にわかると思います。X社の社長も、そのことはわかっていたはずです。
問題は、なぜ「少額のM&Aだから大丈夫だろう」とか「FC本部から提供された契約書だから大丈夫だろう」という油断が生じてしまったのか、なぜ早い段階で弁護士に相談できなかったのかという点です。
この点に関しては、X社が、「本件事業譲渡というM&Aにおいて、何を手に入れたいのか」を明確にできていなかったことが最大の原因だと思います。
X社にとって、本件事業譲渡においては、
- ①事業譲渡後、α地域における学習塾事業を売主であるY社に邪魔されないこと(単なる同業者ではなく、譲り受けた学習塾事業のノウハウや生徒情報を有しているY社に競合されれば、自由競争に勝ちづらいことは明らかです。)
- ②マンモス校の人気講師Aさんが収益を支えている以上、Aさんの確保が必須であること
の2点が死守しなければならない事項でした。
この優先順位さえ明確に意識できておれば、たとえ弁護士でなくても、FC本部から提供された今回の契約書に目を通した際に「この契約書には、自社が死守したい事項が盛り込まれていないのでは?不十分では?」ということに気づけたはずです。
この問題意識を持てて初めて、自社の望む契約内容を勝ち取るための交渉を開始することができるのです。
【成長戦略法務としての契約書の位置づけ】
契約と言うと、多くの方が「将来の紛争を未然に防ぐ」という「防御」としての意味でのみ捉えられますが、私は、それだけの意味ではなく、むしろ契約交渉こそ「攻め」だと考えています。
自由競争の中で勝ち残るためには、少しでも自社に有利な契約条件を勝ち取ることが必須です。しかし、契約交渉は、契約相手方のある話ですから、自社に有利な契約条件を交渉によって勝ち取るためには、しっかりとした交渉戦略と準備が必要になってきます。その意味で、契約交渉も「成長戦略法務」の一環として位置付けられます。とりわけM&Aの領域においては、一般取引と異なり、様々な権利関係がまとめて変動しますので、極めて複雑かつ難解であるからこそ、交渉戦略と準備の必要性がさらに高まります。
皆様も日々色々な契約交渉に触れると思いますが(契約書等の書面があってもなくても関係なく当てはまります。)、今後は、当該取引において「何を手に入れたいのか」「死守したい事項は何か」を明確にすることを意識してみてください(明確にできているか否かは、言語化できるか否かを基準にチェックしてみてください。)。
執筆者:佐藤 康行
佐藤 康行 弁護士法人フォーカスクライド 代表弁護士
2011年に弁護士登録以降、中小企業の予防法務・戦略法務に日々注力し、多数の顧問先企業を持つ。
中でも、人事労務(使用者側)、M&A支援を中心としており、労務問題については’’法廷闘争に発展する前に早期に解決する’’こと、M&Aにおいては’’M&A後の支援も見据えたトータルサポート’’をそれぞれ意識して、’’経営者目線での提案型’’のリーガルサービスを日々提供している。


 06-6210-5533
06-6210-5533 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ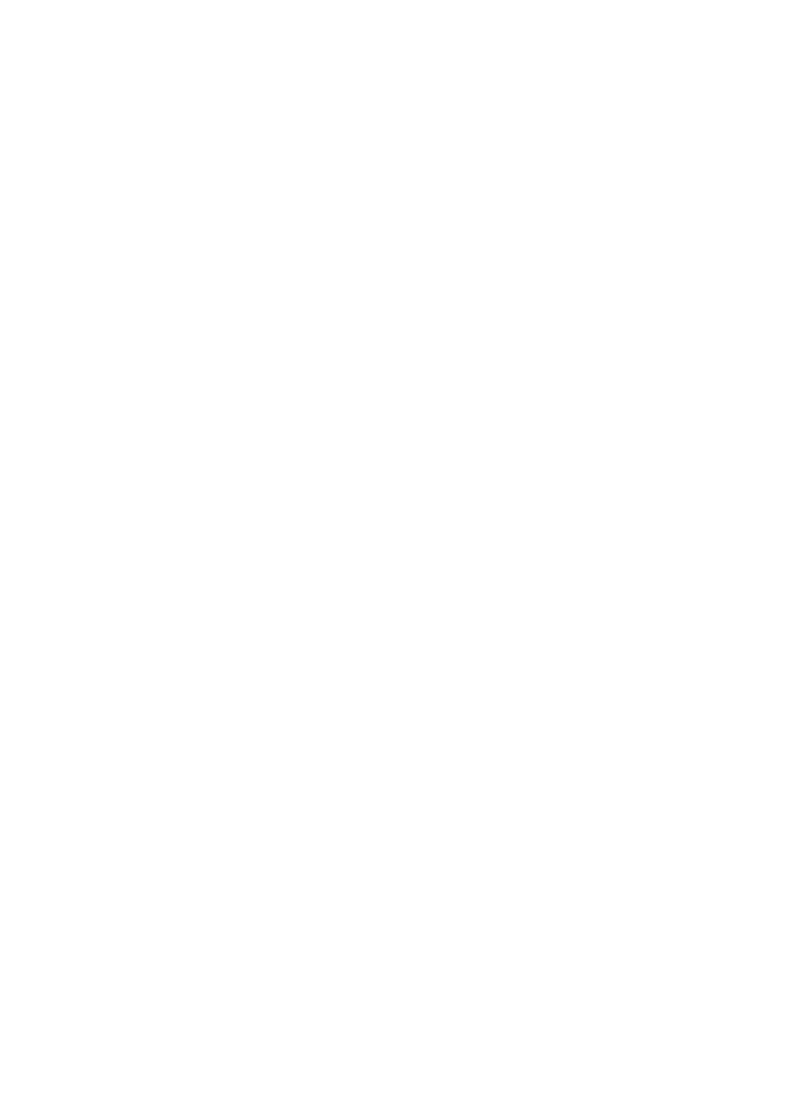 資料ダウンロード
資料ダウンロード